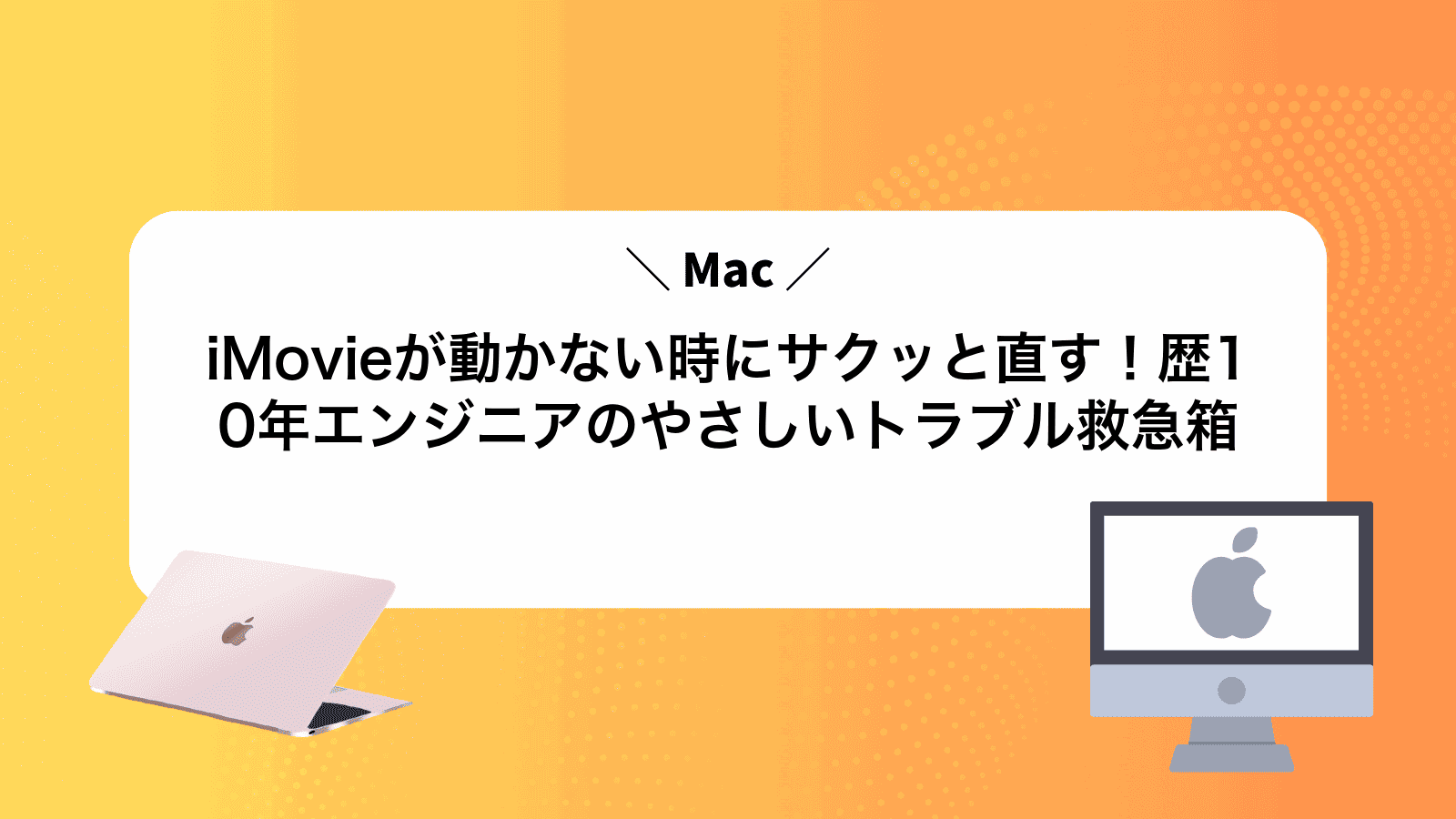作業を急いでいるときにiMovieが突然動かないことが続き、途方に暮れていませんか?
安心してください。このガイドでは、長年Macと向き合って得たトラブル回復のコツを、手を動かしながら試せる順番で紹介します。強制終了から設定ファイルの整理まで網羅しているので、原因が分からなくても短時間で映像編集を再開できます。
今すぐMacをそばに置き、最初の手順からゆっくり実践してみてください。余計な専門知識はいりません。映像づくりの楽しさを取り戻す一歩を、一緒に踏み出しましょう。
iMovieが動かない時にまず試す直し方ぜんぶ
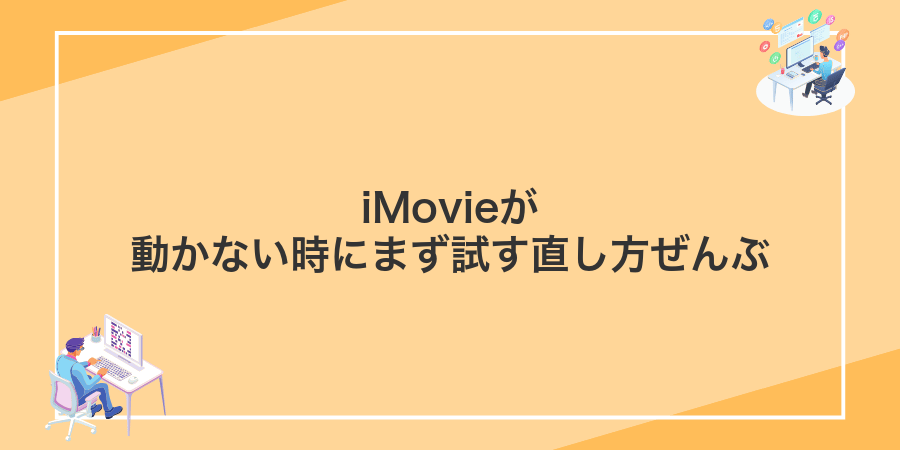
動画編集を進めている途中でiMovieが固まるとガックリしますよね。プロジェクトを保存しておいたのに起動すらしなくなると焦ってしまいます。ここでは、Mac歴10年のエンジニアが実際に試して効果があった方法をまとめました。
- iMovieアプリの再起動
- Mac本体の再起動
- iMovieの最新バージョン確認
- macOSのアップデート適用
- iMovieライブラリの再構築
- iMovieの再インストール
- PRAM/SMCリセット
どれも初めてでもサクッとできる対処ばかりなので、順番に試してみてくださいね。
アプリを強制終了してすぐ立て直す方法
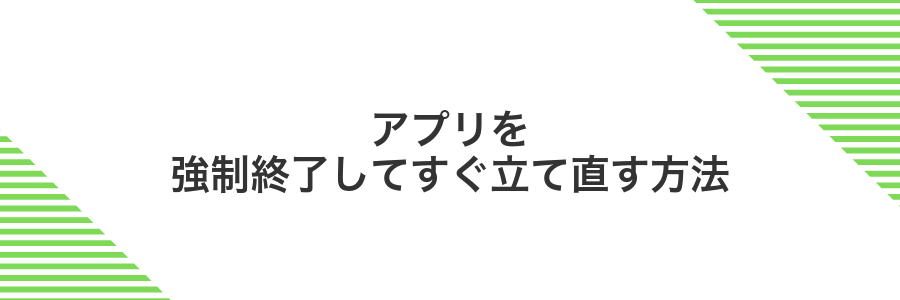
iMovieが固まってしまったら、まずは強制終了してから再起動するのがいちばん手軽です。動作が重くなったり操作を受け付けなくなったりするトラブルでは、メモリや一時データをリセットすることで元のサクサク状態に戻せることが多いです。
強制終了はキーボードショートカットで瞬時にできるうえ、設定やプロジェクトファイルにはほとんど影響しません。画面が固まってボタンも押せない状況や、再生プレビューだけ動かない時などに、まず試してみてください。
①DockのiMovieアイコンを右クリックして「強制終了」を選ぶ
画面下部のDockからiMovieのアイコンを見つけて2本指クリック(またはControlキーを押しながらクリック)します。
表示されたメニューにある「強制終了」を選ぶと、フリーズしたiMovieが即座に閉じられます。
強制終了すると編集中のデータが保存されないので、定期的にプロジェクトを保存しておくと安心です。
②LaunchpadからiMovieをもう一度開く
キーボードのF4キーを押すか、トラックパッドをつまむように3本指と親指でピンチするとLaunchpadが立ち上がります。
Launchpad内のiMovieアイコンを探してクリックします。見つからない場合は下部の検索フィールドにiMovieと入力してください。
③開けなければMacを再起動してから試す
一度Macを再起動すると一時的な不具合がリセットされることがあります。
左上のAppleメニューから再起動を選び、開いているアプリや書類を閉じてから再起動しましょう。
通常の再起動で反応がない場合は、電源ボタンを10秒以上長押しして強制的に再起動してください。強制再起動は緊急時のみ使いましょう。
再起動前に開いている書類やアプリのデータを保存しておきましょう。
ソフトとmacOSを最新にして不具合をつぶす方法
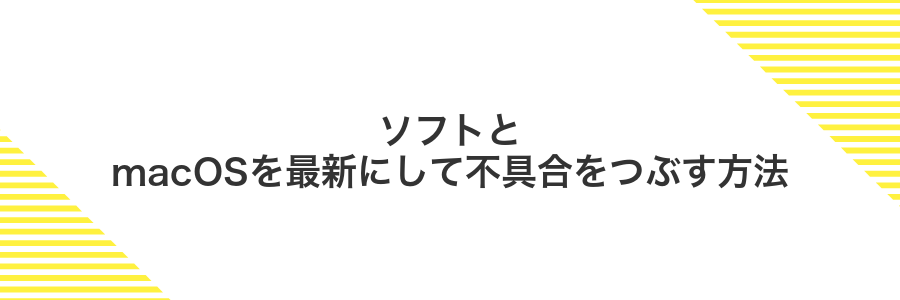
iMovieを触っていると、なんだか調子が悪いなと感じることがあります。そんな時は、iMovieとmacOSを最新バージョンにそろえてみましょう。
ソフトとOSをアップデートすると、知らずに溜まっていた小さな不具合や互換性のズレがリセットされて動作がスムーズになります。
- 互換性の問題を解消:最新のmacOSとiMovieは相性ピッタリなので、予期せぬクラッシュを減らせます。
- 不具合修正が反映:アップデートにはバグ修正が含まれているため、既知のトラブルが解消しやすくなります。
- 新機能が利用可能:最新の便利機能や使い勝手のアップデートを活用できて、編集も楽しくなります。
①AppStoreを開いてiMovieのアップデートを確認する
MacのDockかLaunchpadからAppStoreをクリックして開きます。
右上の検索欄に「iMovie」と入力してEnterキーを押します。
検索結果に表示されたiMovieのアイコン右側に「アップデート」ボタンがあればクリックします。ボタンが「開く」になっている場合はすでに最新です。
②表示がなければ左下の「アップデート」をクリックし一覧を更新する
App Storeを開いたら左下にある「アップデート」アイコンをクリックします。
アプリ一覧が表示されない場合は、もう一度アイコンを押してリストを再読み込みしてください。
③システム設定から「一般」→「ソフトウェアアップデート」でmacOSもチェックする
画面左上のアップルメニューをクリックして「システム設定」を開きます。
サイドバーの「一般」を選んで「ソフトウェアアップデート」をクリックします。
利用できるmacOSアップデートが表示されたら「今すぐ再起動」や「今すぐアップデート」を押してインストールしてください。
安定したWi-Fiに接続しないと最新バージョンが検出されないことがあります。
設定ファイルをリセットして初期状態に戻す方法
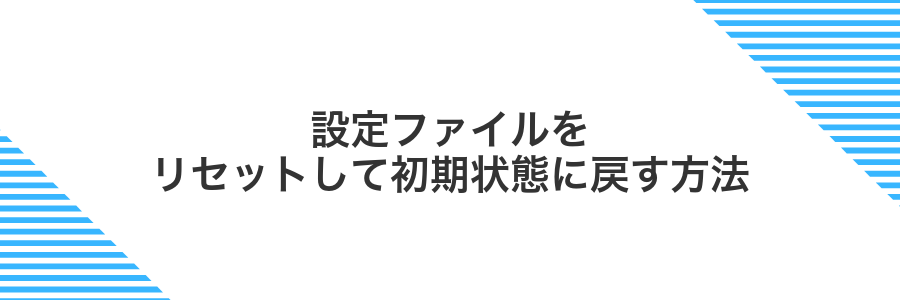
設定ファイルをリセットするとiMovieの操作履歴やウィンドウ配置をすっきり初期化できます。たとえば起動時に固まったりツールが反応しづらくなる場合、内部データの設定に不整合が起こっていることがあります。
この方法は設定だけをリセットするため、作成中の動画プロジェクトやメディアファイルには影響しません。設定まわりのトラブルを手早く解消したいときにおすすめです。初期状態に戻すことで、再び快適な編集環境が手に入ります。
①Finderでメニューバー「移動」→「フォルダへ移動」をクリック
Finderをアクティブにして、画面上部のメニューバーにある「移動」をクリックします。
表示されたメニューから「フォルダへ移動」を選んで、ダイアログを呼び出してください。
キーボードショートカット⌘+Shift+Gを使うと、同じ操作をすばやく実行できます。
②入力欄に~/Library/Preferencesと打ちEnter
Finderがアクティブな状態で、キーボードからShift+Command+Gを押すと「フォルダへ移動」ウインドウが開きます。
入力欄に~/Library/Preferencesと打ち込んでEnterキーを押してください。
③com.apple.iMovieApp.plistをデスクトップへ移動しMacを再起動する
設定ファイルが原因でiMovieが正しく動かない場合、plistファイルをリセットすると改善することがあります。ここでは「com.apple.iMovieApp.plist」を一時的にデスクトップへ移動して、Macを再起動する手順を紹介します。
デスクトップ左上のFinderアイコンをクリックし、メニューバーの「移動」→「フォルダへ移動」を選びます。
入力欄に~/Library/Preferencesと入力して「移動」を押します。
「com.apple.iMovieApp.plist」を見つけたら、そのファイルをドラッグしてデスクトップへ移動します。これで元の設定は保持されたままリセットできます。
画面左上のアップルメニューから「再起動」を選んで、Macを再起動します。
移動したplistはiMovie起動時に自動で再作成されますが、元の設定を戻したい場合はデスクトップからPreferencesフォルダへ戻してください。
ライブラリを再構築して壊れたプロジェクトを救う方法
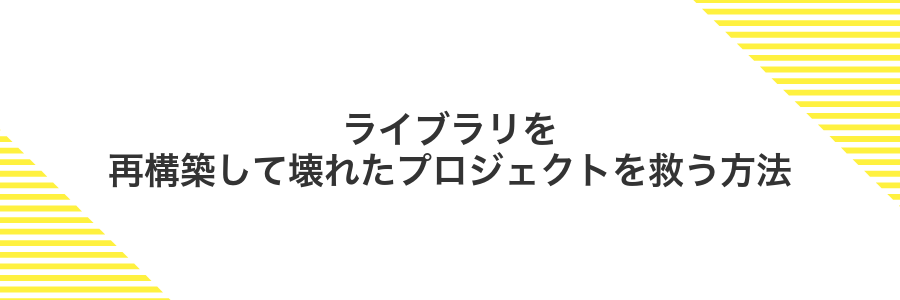
プロジェクトやイベントが開けなかったり、クリップのサムネイルが真っ黒になったときは、ライブラリの再構築が頼りになります。データベースをリセットしつつ、もともとの映像や編集情報をそのまま残して正常な状態へ戻せるんです。
- データベースのクリーンアップ:壊れた参照や重複を削除してリンクを新しく作り直します。
- 素材と編集情報を維持:ムービークリップやエフェクト、タイムラインは一切消えません。
- スピーディーな復旧:ライブラリ容量にもよりますが数分~十数分で完了します。
- システム標準の方法:公式の方法なので安心感があります。
ライブラリ再構築の前にFinderで対象ファイルをコピーしておくと、念のため元の状態に戻せます。
①iMovieを起動しながらOptionキーを押し続ける
Optionキーを押しながらiMovieを起動すると、環境設定ファイルがリセットされて動作トラブルが解消しやすくなります。
メニューバーの「iMovie」→「終了」を選んでアプリを閉じてください。
DockやSpotlightからiMovieアイコンをクリックして、キーを離さずにそのまま待ちます。
表示されたダイアログで「環境設定をリセット」をクリックして、初期状態に戻します。
Optionキーを離すとリセット処理が中断するので、ダイアログが表示されるまで押し続けること。
②出てきたウインドウで「ライブラリを新規作成」を選ぶ
ウインドウが開いたらライブラリを新規作成をクリックします。表示されたフォームにわかりやすい名前を入力し、保存場所を選ぶと新しいライブラリが作成されます。
③元のライブラリをドラッグして素材をインポートし直す
iMovieが動いているとインポートがうまくいかないことがあります。まずはアプリを完全に閉じてから、Finderでユーザの「ムービー」フォルダを開きます。
拡張子が「.imovielibrary」のファイルを見つけます。ライブラリ名に日付やプロジェクト名が入っているので、間違えないように注意してください。
ライブラリファイルをFinderからiMovieのプロジェクトブラウザへ直接ドラッグします。これで素材の再インポートが始まります。
インポートが終わったら、再生や編集画面を開いて動作チェックします。素材が正常に表示されれば完了です。
大きなライブラリは読み込みに時間がかかることがあります。素材はローカルストレージに置いて操作するとスムーズです。
ストレージを空けて動作を軽くする方法
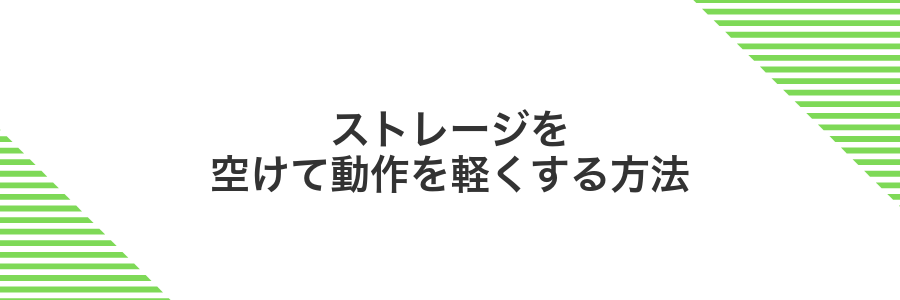
動画をたくさん扱うと一時ファイルが増えて、気づいたらストレージがぎゅうぎゅうに。そんな状態だとiMovieもカクつきやすくなります。不要な写真や動画を外付けHDDに移すだけで、スイスイ編集できるようになることが多いです。特に大きなプロジェクトを開く前には50GB以上の空きを意識すると安心感がアップします。
①アップルメニュー「このMacについて」→「ストレージ設定」をクリック
画面左上のアップルマークをクリックして「このMacについて」を選びます。
表示されたウインドウのストレージタブを開き「ストレージ設定」をクリックします。
②不要な大容量ファイルを左サイドバーから順に削除する
iMovieを開いたら左サイドバーの「マイメディア」アイコンをクリックします。
右上にあるソートメニューを押して「ファイルサイズ順」を選び、大きいものから一覧に並べ替えます。
容量が大きくてもう使わないクリップや音声を見つけたら、そのファイル名にマウスを重ねてゴミ箱アイコンをクリックします。
削除確認が出たら「削除」を選ぶと完全にファイルが消え、プロジェクトの容量をスッキリ軽くできます。
③ゴミ箱を空にしてMacを再起動する
まずゴミ箱にたまった不要ファイルを消してから、Macをまっさらな状態で再起動しましょう。
- 画面左下のDockからゴミ箱を右クリックして「ゴミ箱を空にする」を選ぶ
- 表示される確認ダイアログで「ゴミ箱を空にする」をクリックする
- 左上のAppleメニューをクリックして「再起動」を選ぶ
- 再起動ダイアログで「再起動」をクリックして完了
大容量のファイルがあるとゴミ箱を空にする処理に時間がかかることがあります。
トラブル解決後にもっと快適!iMovieを安定させるひと工夫
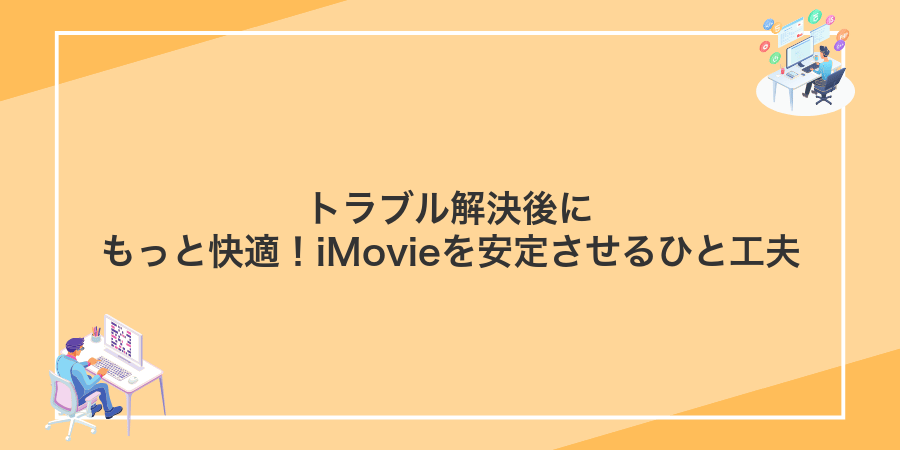
トラブルを乗り越えたら、もうひと手間かけてiMovieをもっと気持ちよく使いましょう。
| ひと工夫 | メリット |
|---|---|
| ライブラリの定期アーカイブ | 不要素材を整理して作業中の読み込みを軽くする |
| キャッシュ手動クリア | 溜まった一時ファイルを削除して起動や書き出しを速くする |
| 外部ドライブへのメディア移動 | 本体の空き容量を確保して安定動作をキープする |
ライブラリを外付けドライブに整理して内部SSDを守る
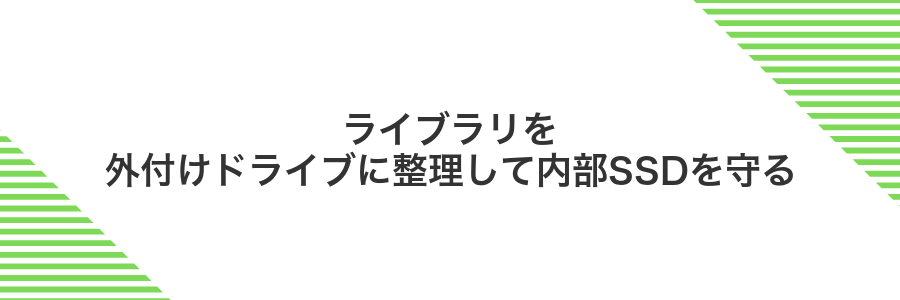
iMovieのライブラリは動画素材やレンダリングファイルであっという間にサイズが増えて、内部SSDの空き容量をギリギリに追い込むことがあります。空き容量が少ないと読み込みがもたついたり、保存時にエラーが出たりして、結果としてアプリが動かない原因にもなりかねません。
外付けドライブにライブラリを移しておくと、内部SSDの負担をグッと減らせます。特にUSB-CやThunderbolt接続の高速ドライブを選ぶと、ほとんど内蔵SSDと同じ感覚で作業できるのがエンジニア目線のおすすめポイントです。
外付けSSDをAPFSでフォーマットする
外付けSSDをMacに接続してから、LaunchpadやSpotlightでディスクユーティリティを起動します。
左サイドバーから外付けSSDのデバイス名をクリックして選びます。パーティション名ではなく、デバイス本体を選ぶのがポイントです。
画面上部の「消去」を押して、フォーマット設定ダイアログを開きます。ここで間違えると全て消えるので要注意です。
フォーマット欄からAPFSを選び、名前を入力して「消去」をクリックします。数秒待てば完了です。
消去を実行するとSSD内のデータがすべて消えます。必ず必要なデータはバックアップしてください。
新しいiMovieライブラリを外付けに作る
ディスクユーティリティを開いて外付けドライブがAPFSでフォーマットされているか確かめます。
Finderで外付けドライブを開き、「iMovieライブラリ」という名前の新規フォルダを作ります。
iMovieを起動するときにOptionキーを押し続けるとライブラリ選択画面が出ます。「新規ライブラリ」をクリックし、先ほど作ったフォルダを選んで保存してください。
外付けドライブを再フォーマットすると中のデータがすべて消えます。重要なファイルは必ずバックアップしてください。
プロジェクトをドラッグして移動する
Finderを使ってiMovieライブラリ内のプロジェクトをドラッグして別フォルダに移動します。移動後にiMovieを再起動するとプロジェクトの読み込みがリフレッシュされて動作が安定しやすくなります。
まずiMovieを完全に閉じてからDockのFinderアイコンをクリックしてウィンドウを表示します。
ホームフォルダの「ムービー」内にある「iMovieライブラリ」を右クリックし「パッケージの内容を表示」を選びます。表示されたフォルダから移動したいプロジェクトをドラッグしてデスクトップなど別のフォルダにコピーします。
移動中はデータコピーに時間がかかることがあるので他の作業を控えておくと安心です。
プロジェクトを小分けにして編集負荷を減らす
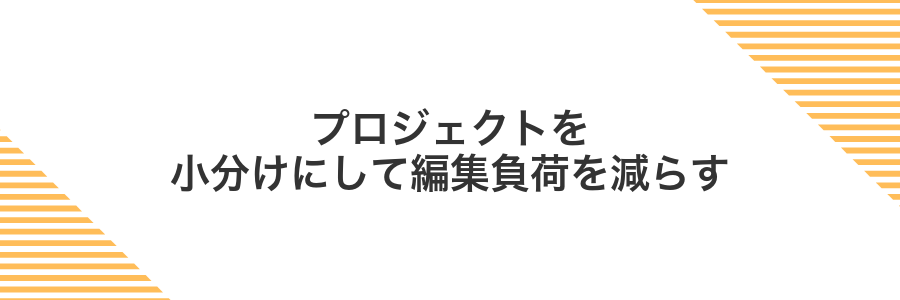
大きな動画を一つのiMovieプロジェクトで詰め込んでいると読み込みや書き出し時に処理が止まりやすくなります。そこで作業しやすい長さに分割して、それぞれを独立したプロジェクトとして扱う方法が有効です。
短いクリップごとに3~5分程度のプロジェクトに分けると編集操作が軽くなりUIの反応がスムーズになります。完成後は各プロジェクトを書き出してタイムライン上でつなぎ合わせるだけで一本の作品にまとめられます。
長編動画を章ごとに別プロジェクトへ分割する
イベントブラウザで該当の長編プロジェクトを右クリックし「複製」を選ぶと元データを安全に残せます。
イベントブラウザ内の複製プロジェクトをダブルクリックしてタイムラインを開きます。
再生ヘッドを分割したい位置に移動し、対象クリップを選択して右クリック→「クリップを分割」を選びます。
分割後に残したい章以外のクリップを選んでDeleteキーで消去します。
イベントブラウザに戻り、プロジェクト名をダブルクリックして該当の章タイトルに書き換えます。
注意点:分割しすぎると管理が煩雑になるため、あらかじめ章数を絞っておくと使いやすくなります。
書き出し後に一つの新規プロジェクトで合体する
iMovieを起動して画面上部の「+」アイコンから「ムービー」を選びます。タイトルやテーマはあとで調整できるので気軽に進めてください。
ライブラリ欄の「メディアをインポート」ボタンをクリックして、先ほど書き出した動画ファイルをすべて選択します。複数選択は⌘キーを押しながらクリックです。
インポートしたクリップをタイムラインにドラッグ&ドロップして、書き出し順やシーン順に並べます。順番を間違えないように、ファイル名に番号を振っておくと便利です。
TimeMachineで自動バックアップを設定して安心をキープ

TimeMachineはMacに元々備わっているバックアップ機能です。一度外付けドライブをつないで設定しておくと、あとは自動でデータを保存してくれるので、iMovieのプロジェクトが消えたりシステムアップデートで動かなくなったときも過去の状態にサクッと戻せます。編集作業に集中しながら万が一のトラブルに備えられるのがうれしいポイントです。
外付けHDDを接続しTimeMachineをオンにする
USB-CやThunderboltケーブルを使って外付けHDDをMac本体のポートにしっかり差し込んでください。
「アプリケーション>ユーティリティ>ディスクユーティリティ」を開き、HDDを選択して「消去」をクリック。「フォーマット」をAPFSにして名前を付けてください。
アップルメニューから「システム設定」を選び、「一般>TimeMachine」をクリックして設定画面を表示させてください。
「バックアップディスクを選択」をクリックし、先ほどフォーマットした外付けHDDを選んで「ディスクを使用」を押してください。
HDDをつなぐポートによっては給電不足になることがあります。バスパワータイプはセルフパワータイプより安定性が高いです。
「オプション」でiMovieライブラリが対象に入っているか確認する
iMovieをOptionキーを押しながら起動すると、ライブラリ選択画面が現れます。ここで対象のライブラリがリストに含まれているかかんたんにチェックしましょう。
DockまたはLaunchpadでiMovieのアイコンをOptionキーを押しながらクリックしてください。ライブラリを選ぶダイアログが開きます。
表示されたリストから目的の
リストにないときはダイアログ下部の「その他」をクリックし、Finderでムービーフォルダ内の
よくある質問
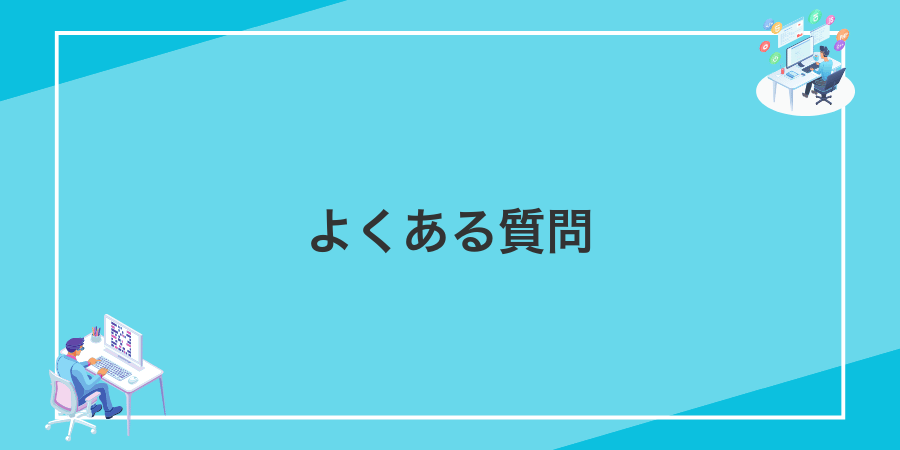
iMovieが起動しない
- iMovieが起動しない
設定ファイルの破損で止まっているケースがよくあるので、Finderから~/Library/Preferences/com.apple.iMovieApp.plistをゴミ箱へ移してみてください。起動後に新しいplistが自動生成されるので、不要なキャッシュや設定の不整合をリセットできます。
プロジェクトが読み込めない
- プロジェクトが読み込めない
ストレージの空き不足や外付けドライブのマウント不良が原因かもしれません。まずはディスクユーティリティでアクセス権を修復し、外部ドライブを再接続してください。それでもダメなら別のフォルダへプロジェクトフォルダ丸ごとコピーして再読み込みを試しましょう。
動画のエクスポートが終わらない
- 動画のエクスポートが終わらない
並列処理が負荷をかけて止まることがあるので、プレビューを一時停止してから書き出しを試してください。それでも時間がかかるときは、エクスポート設定を「1080p」に下げるとCPU負荷が下がってスムーズになります。
iMovieが開く前に落ちるのはなぜ?
アプリを起動する前に落ちるときは、まず内部の設定ファイルがゴチャゴチャになっていることが多いです。
とくにOSをアップデートした直後は、iMovieのバージョンと合わずに起動直後でクラッシュしやすいです。また、サードパーティ製のプラグインが入っていると、相性が悪くて固まる場合もあります。
ほかにも、ディスクの空き容量がギリギリだったり、キャッシュが増えすぎて読み込みに失敗したりすると、落ちやすくなります。こうした原因を知っておくと、あとで対処がずっとラクになります。
プロジェクトだけが開けない時はどうする?
突然、大事なプロジェクトだけ開けなくなって戸惑うことありますよね。他のムービーは普通に使えるのに、このファイルだけ反応しないときは、つい首をひねりたくなります。
このケースではライブラリの修復やメディアの再リンク、バックアップからの復元を試すと効果的です。特定のプロジェクトだけ直せるので、他の設定や素材に影響を与えずにサクッと復旧できます。
再インストールすると素材は消える?
再インストールはiMovieアプリ本体の入れ替えだけなので、既存のプロジェクトや素材はそのまま残ります。iMovieが保存しているメディアは~/Movies/iMovieライブラリ.imovielibraryというライブラリファイル内に格納されていて、アプリを削除しても消えません。
とはいえ、ライブラリを誤ってゴミ箱に入れると素材が失われるので注意しましょう。再インストール前にTime Machineや外付けドライブでバックアップを取っておくと安心です。
ライブラリファイルはアプリ本体と別扱いです。慌てずバックアップを確認してから作業しましょう。
外付けドライブから起動するときの注意点は?
外付けドライブからmacを起動すると、内蔵ディスクの不調を気にせずにOSのチェックや修復が試せるので便利です。ただし、いくつか押さえておきたいポイントがあります。
- ドライブのフォーマットはAPFS+GUIDパーティションにする
- Apple Silicon搭載Macでは、リカバリ画面のスタートアップセキュリティ設定で外部起動を許可しておく
- USB-C/Thunderbolt接続は対応ケーブルとポートを選ぶと安定する
- SSDなら速度が速いのでiMovieの編集中も快適に動作する
- 終了時はドライブを安全に取り出す操作を忘れずに
これらを守ると、外付け起動で作業中に慌てずに済みます。
まとめ
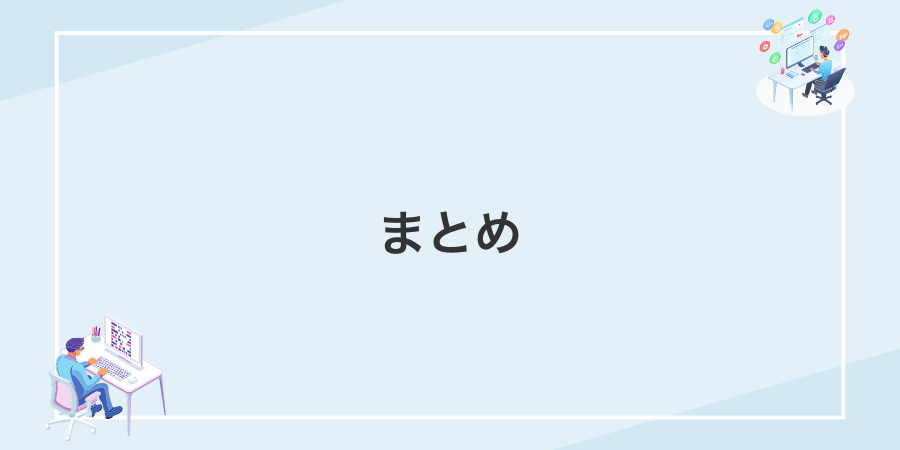
iMovieが動かない時は、以下の順番でチェックと操作を行うとほとんどの場合解決できます。
- Macを再起動して一時的な不具合をリセット
- iMovieとmacOSを最新版にアップデートして互換性を確保
- 設定をリセットして環境を初期状態に戻す
- キャッシュ削除で動作をスムーズに
- プロジェクトデータを整理・書き出しして容量を最適化
これで不具合が解消し、また楽しく動画編集を進められるはずです。新しいクリエイティブな作品作りを思い切り楽しんでください。