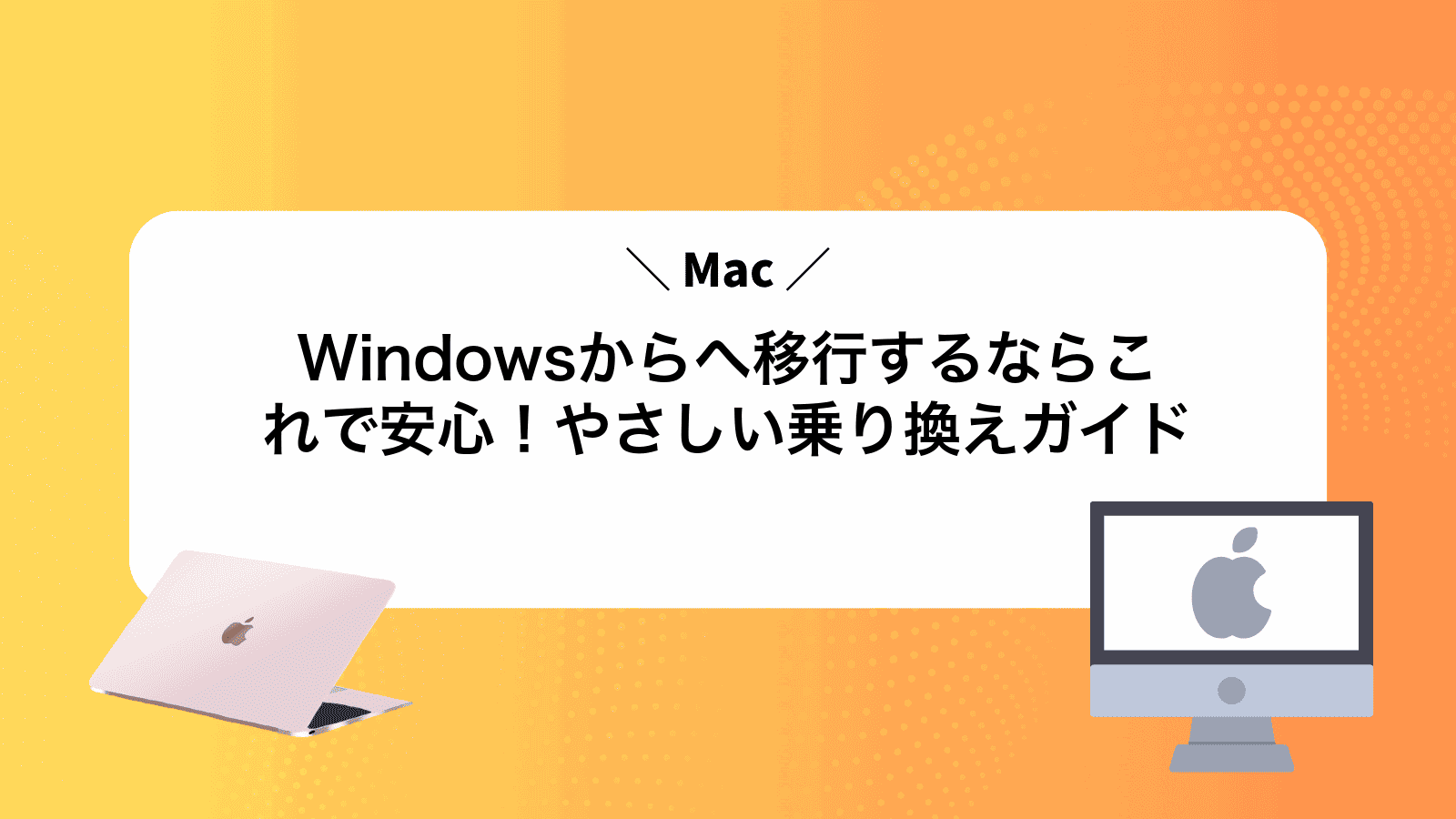Windowsで長年慣れた環境からMacへの移行を考えつつ、データや使い勝手が変わる不安で手が止まっていませんか?
このガイドは、多数のパソコンを乗り換えてきた経験を基に、迷わず進める手順と作業後すぐ役立つ応用ワザをまとめています。ファイルの取りこぼしも設定漏れも防げるため、短時間で新しいMacが自分仕様になります。
まずは最初のステップを確認し、ご自宅のネットワークや外付けドライブを手元に置いてください。読みながら手を動かせば、作業後すぐMacで快適な作業や趣味を始められます。
WindowsパソコンからMacへデータと設定を移すやさしい手順
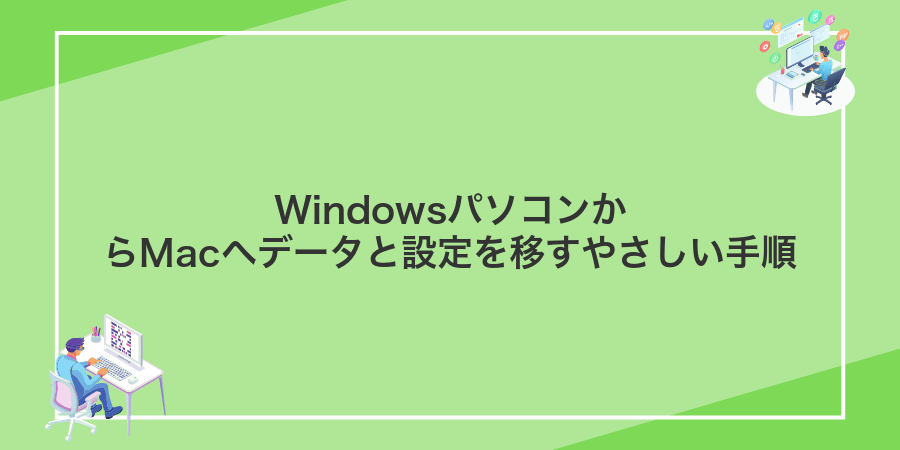
WindowsパソコンからMacへ移行するときは、大きく分けて次の方法があります。ひとつずつご紹介しますね。
- Migration Assistantを使う:同じネットワークに接続したWindowsとMacを手軽につなげる方法です。
- 外付けドライブ経由で手動コピー:大きなファイルやカスタム設定を自由に移行できます。
- クラウドサービスで同期:OneDriveやDropboxを使ってフォルダごとにじわっと移し替えます。
それぞれにメリットがあるので、使いたい方法や利用できる環境にあわせて選んでください。
ネットワーク移行は設定とデータをまとめて移せますが、初回は転送に時間がかかることがあります。
プログラマー目線の小ワザとして、移行前に不要ファイルや古いバックアップを整理しておくと、後でディスク容量が足りなくなる不安が減りますよ。
大まかな流れをつかんだら、次は各手順を順番に進めて快適なMacライフをスタートしましょう。
Apple公式移行アシスタントを使う方法
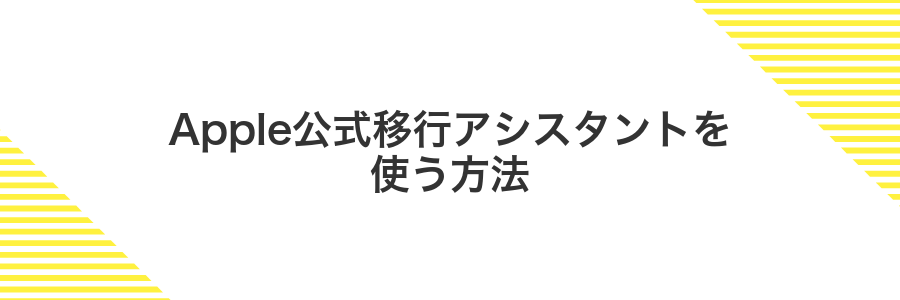
Apple公式の移行アシスタントはWindowsパソコンとMacを同じネットワーク、またはUSB-C/Thunderboltケーブルでつなぐだけで、大量のデータやアカウント情報、アプリ設定をそのまま引き継げます。初めて使うときも安心のステップガイドつきなので、いちいち手動で探す必要がありません。
プログラマーにはソースコードや環境設定(たとえばGitの設定ファイルやターミナル設定)を丸ごと移行できるのがうれしいポイントです。ネットワーク越しに転送する場合も、有線接続なら数十GBのデータが数時間で終わることがあり、大容量ファイルを扱う人にも最適です。
①WindowsPCで移行アシスタントをダウンロード
お使いのWindowsPCでブラウザを立ち上げて、Apple公式サイトの「Windows移行アシスタント」ダウンロードページに移動します。
ページ内の最新バージョンリンクをクリックして、.msiインストーラーを任意のフォルダに保存してください。
保存が完了したらダウンロードは終了です。このあとインストールに進みます。
②Macで移行アシスタントを起動してWindowsを選ぶ
MacのLaunchpadを開き「その他」フォルダ内にある移行アシスタントをクリックしてください。
画面の案内に従いApple IDのパスワードを入力して「続ける」を押します。
「Windows PCから」を選び、表示された確認画面で再度「続ける」をクリックします。
MacとWindowsが同じネットワーク内に接続されているか必ず確認しましょう。
③同じWiFiまたはLANケーブルで両方をつなぐ
画面右上のWiFiアイコンをクリックして、移行先Windowsと同じSSIDに接続してください。有線接続を使う場合はThunderbolt→EthernetアダプタにLANケーブルを挿し、システム設定のネットワークから「Ethernet」を選びます。
タスクバーのネットワークアイコンからMacと同じSSIDを選んでつなぎます。有線の場合はLANケーブルをルーターやハブ経由で接続し、インターネットアクセスの表示が出ればOKです。
WiFiが混雑しているときは有線接続が速くて安定します。
④転送したいユーザーデータをチェックで選ぶ
Migration Assistantの「転送する情報を選択」画面で、ユーザーアカウントやアプリケーション、書類などが一覧で表示されます。ここから新しいMacに持っていきたい項目にチェックを入えていきましょう。
まずは画面左のユーザー名やアプリ、書類といったカテゴリをざっと眺めてください。転送対象の全体像がつかめます。
カテゴリ名の横にある三角アイコンをクリックすると中身が見えます。プログラミング環境ならホームフォルダ内の隠しフォルダ(.sshや.config)にもチェックを入れると、後で設定し直す手間が減ります。
大容量の動画やバックアップファイルなど、いま必要ないものはチェックを外しましょう。転送時間とディスク容量の節約になります。
すべて選択したあと、画面下部の合計サイズを必ず確認してください。空き容量が足りないと途中で止まることがあります。
⑤Macのパスワードを設定して転送を開始
Migrationアシスタントで求められたダイアログにMacのログインパスワードを入力します。
入力後「続ける」をクリックするとデータ転送がスタートします。進行状況バーが動き始めたことを確認してください。
管理者権限のあるユーザーで作業を行わないとパスワード入力ができないため注意してください。
⑥完了メッセージを確認してMacを再起動
Migration Assistantがファイル転送を終えると「転送が完了しました」のメッセージが表示されます。
完了メッセージを確認したら、画面左上のAppleメニューをクリックして「再起動」を選びましょう。
再起動を忘れると移行データの反映がずれることがあるので、必ず実行してください。
iCloudを使って軽やかに移す方法
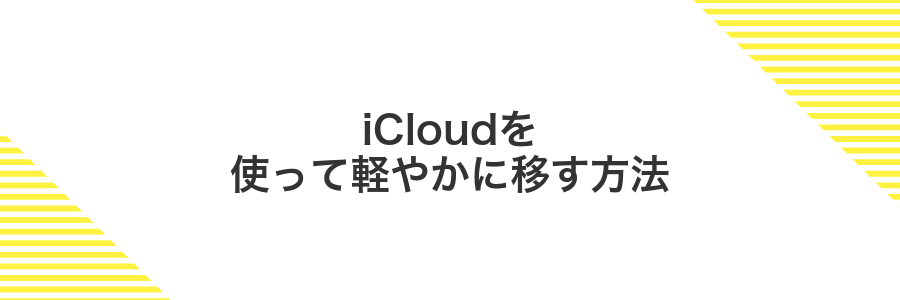
iCloudはApple公式のクラウドサービスで、インターネットを使って写真や書類を自動で同期できます。
Windows用のiCloudアプリを入れれば、パソコン上のフォルダをそのままiCloud Driveとつなげられます。
同期は差分だけアップロードする仕組みなので、二回目以降はスピーディーでストレスなく進みます。
- 設定がシンプルでApple IDがあればすぐに始められる
- 写真や書類をフォルダ構成そのままで移せる
- 差分同期により大量ファイルでも効率的に更新できる
- 容量不足は月額プランで簡単に追加できる
①WindowsPCでiCloudを最新版にアップデート
Microsoft Storeを開いてウインドウ左下のライブラリをクリックします。
ライブラリ画面で「iCloud」を探して更新ボタンを押します。
完了したらPCを再起動して、iCloudが最新版になっているか確かめてください。
Microsoft Store版でない場合はApple Software Updateからアップデートしてください。
②写真と連絡先の同期をオンにする
画面左上のアップルメニューから「システム設定」を開きます。
サイドバーで自分の名前(Apple ID)を選び、iCloudをクリックしてください。
表示されたiCloudの一覧から「写真」と「連絡先」のスイッチをそれぞれクリックしてオンにします。
これでiCloud経由でクラウドにアップされた画像と連絡先がMacの「写真」アプリや「連絡先」アプリに自動で反映されます。
写真のデータ量が多いと同期に時間がかかります。Wi-Fi接続が安定している場所で行い、バッテリー残量にも余裕をもたせてください。
③Macの初期設定画面で同じAppleIDでサインイン
初期設定画面で表示されたAppleIDの欄に移行前と同じAppleIDを入力します。
続いてパスワードを入力して「次へ」をクリックします。
二要素認証が有効な場合はiPhoneや別のデバイスに届いた確認コードを入力してください。
同じIDを使うとiCloudの連絡先や写真が自動で同期されてMacの使い始めが滑らかになります。
二要素認証コードが届かない場合はiPhoneの設定→ユーザ名→パスワードとセキュリティから確認できます。
④FinderのサイドバーからiCloudDriveを開きデータを確認
画面下のDockにあるFinderアイコンをクリックしてウインドウを開いてください。
左側のサイドバーでiCloud Driveを探してクリックします。
中にあるフォルダーやファイルをダブルクリックし、正しく同期されているかひとつずつチェックします。
iCloud Driveがサイドバーに表示されない場合は「システム設定>自分の名前>iCloud」からiCloud Driveをオンにしてください。
外付けドライブとTimeMachineを使う方法
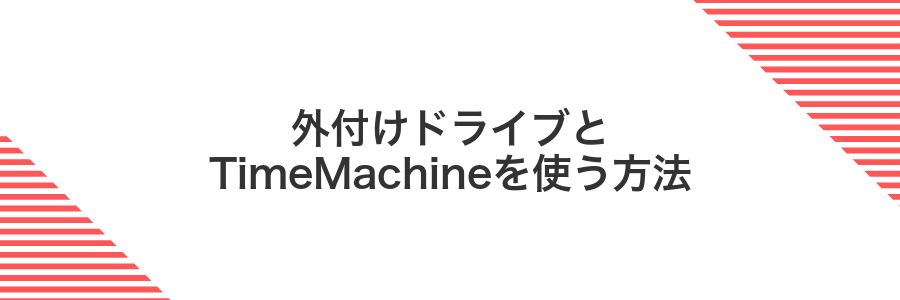
外付けドライブを使った方法は、あらかじめUSB接続やThunderbolt接続のドライブをMacに差して、Time Machineのバックアップ先に設定しておくだけで準備完了です。Windows側の大事なデータはドラッグ&ドロップで外付けドライブにコピーしておき、そのあとMacでTime Machineからバックアップをさくっと読み込むと、フォルダ構造やファイルの更新日もそのまま引き継げます。
このやり方のいいところは、ネット回線を気にせず一気にデータを移せる点です。動画素材や開発プロジェクトなど容量が大きくても安定してコピーできるので、プログラマーとしても安心感があります。さらにTime Machineに常時バックアップを残しておけば、後から追加のファイルを移したり誤操作で消したデータを復元したりと、日々の作業もスムーズになります。
①Windowsで外付けドライブをexFATでフォーマット
外付けドライブをWindowsに差し込んで、タスクバーのエクスプローラーアイコンをクリックします。
左側のドライブ一覧から該当の外付けドライブを探し、右クリックしてフォーマットを選びます。
フォーマット画面のファイルシステム欄でexFATを選びます。割り当て単位サイズはデフォルトのまま、ボリュームラベルはわかりやすい名称にしておくとMacで扱うときに便利です。
クイックフォーマットにチェックを入れて開始ボタンを押します。警告が表示されたら中のデータが消えることを確認してOKをクリックしてください。
完了後に閉じるを押せば準備は完了です。念のためMacに挿して読み書きできるか試してみましょう。
古いWindowsや家電製品だとexFAT未対応の場合があるため、使い始める前に動作確認をしておくと安心です。
②移行したいフォルダをドラッグして保存
外付けドライブをMacに接続してFinderで開いたら、移したいフォルダをクリックしたまま移行先のデスクトップや任意のフォルダへドラッグしてください。
Finderのウィンドウを2つ並べるとドラッグ先が見やすくなります。
大きなフォルダはコピーに時間がかかるので、途中でスリープしないようにシステム環境設定の〈バッテリー〉で「ディスプレイのオフにするまでの時間」を長めに設定しておくと安心です。
③ドライブを安全に取り外してMacに接続
Windowsのタスクバー右下にあるUSBアイコンをクリックして、取り外したいドライブ名を選びます。「ハードウェアを安全に取り外しました」と表示されたら準備完了です。
ケーブルをゆっくり引き抜いたあと、最新のmacOS Sonoma搭載Macにしっかり差し込みます。数秒でFinderのサイドバーにドライブ名が表示されれば接続成功です。
念のため、ディスクユーティリティを開いてドライブが認識されているか確認すると安心です。
取り外す前にファイルの読み書きが完了しているか確かめてください。途中で抜くとデータが壊れる可能性があります。
④Finderでファイルをコピーしアプリを起動テスト
DockやメニューバーからFinderを開き、サイドバーの「ダウンロード」などアプリを移したフォルダに移動してください。
移したいアプリのフォルダを見つけたら、/Applicationsフォルダへドラッグ&ドロップします。
コピーが完了するまで焦らず待てばOKです。
Applicationsフォルダを開いて、コピーしたアプリをダブルクリックしてみましょう。
もし「開発元が未確認です」と出たら、アプリをcontrolキー+クリック→開くで起動してください。
問題なく起動して設定画面やメイン画面が表示されたらコピー成功です。
Finderでドラッグする際に、別ドライブや外付けSSDからのコピーは時間がかかる場合があります。完了するまではFinderを閉じないでください。
Macへ移行したあとすぐ試したい応用ワザ
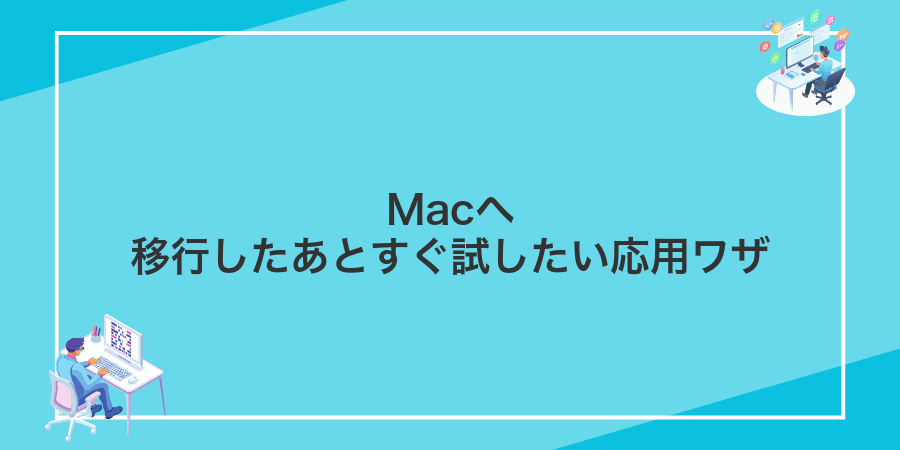
Macへ移行したあと、すぐに使える応用ワザを集めました。それぞれの特徴と活用シーンをチェックして、日々の作業をもっと快適にしてみましょう。
| 応用ワザ | 役立つ場面 |
|---|---|
| Spotlightの絞り込み検索 | ファイルや設定をすばやく探したいときに、条件を細かく指定して瞬時に目的地へジャンプできます。 |
| ショートカットアプリで自動化 | よく使うフォルダ整理やリネーム作業をワンクリックで実行して、手動作業をぐっと減らせます。 |
| ターミナルでbrew管理 | Homebrewを使って開発ツールやアプリをまとめてインストールすることで、セットアップを一気に完了できます。 |
| Quick Lookでプレビュー拡張 | 拡張機能プラグインを追加して、動画やMarkdownなどもFinder上でサクッと中身を確認できます。 |
これらの応用ワザは初めてでもすぐに導入しやすいものばかりです。気になったものから順番に試して、自分好みの使い勝手を見つけてみてください。
ショートカットキーをWindows風に近づける
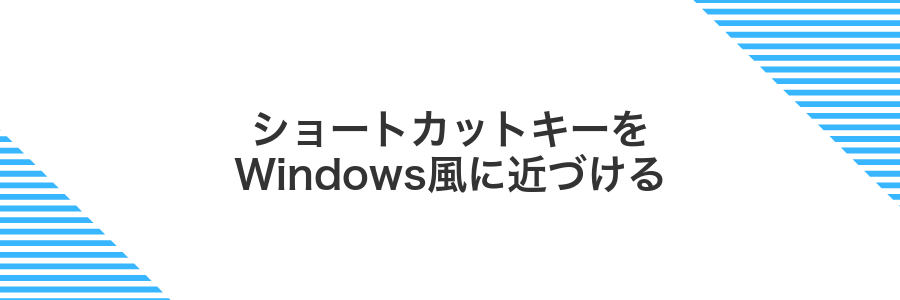
Macのショートカットは⌘キー中心だけど慣れないとドキドキしますよね。Ctrl+C/Vでコピー&貼り付けといったWindowsの感覚をキープしたいときは、修飾キーの入れ替えが手軽で効果バツグンです。
設定はシステム設定>キーボード>修飾キーからすぐに変更できますし、もっと細かいカスタマイズを楽しみたいならKarabiner-Elementsがおすすめです。Ctrlを⌘にマッピングしたり、CapsLockをCtrlに置き換えたりすれば、手が自然に動く快適さを取り戻せます。
システム設定のキーボードで修飾キーを入れ替える
WindowsのCtrlキー操作に慣れていると、Macでのコピー&ペーストなどがちょっと遠く感じますよね。その違和感をなくすために、修飾キーを入れ替えてみましょう。
画面左上のAppleメニューからシステム設定を選びます。
サイドメニューの「キーボード」を探してクリックします。
画面下部にある「修飾キー…」ボタンを押して設定画面を開きます。
プルダウンメニューでControlキーにCommandを、CommandキーにControlを設定したら「完了」を押します。
外付けキーボードを使う場合は、設定画面の上部から該当のデバイスを選ぶのを忘れないようにしてください。
KarabinerElementsをインストールしてさらなるカスタム
キーボード周りをもっと自分好みに変えたいときにはKarabinerElementsが強い味方になります。カスタムキー割り当てや複雑なショートカットも簡単に作れるので、Macのキーボード操作がぐっと楽しくなります。
ターミナルを開いて以下を入力すると最新版がすぐ手に入ります。Homebrew未導入の場合は先にbrewの公式手順に沿って準備してください。
brew install --cask karabiner-elementsKarabinerElementsがキーボードを扱えるように「システム環境設定」→「セキュリティとプライバシー」→「入力監視」でチェックを入れます。再起動が求められたら素直に従いましょう。
アプリを開いたら「Complex Modifications」タブを選び、「Add rule」から公開されているプリセットを導入できます。必要に応じて自分用のJSONを置くとさらに自由自在です。
注意点:JSONを手動で書くときは構文エラーが原因で無効になることがあります。公式サンプルをコピペして編集すると失敗しにくいです。
ExcelなどでCtrl+Cが使えるか確認する
Excelを起動して新規ブックを作成し、セルA1に「テスト」と入力します。
セルA1を選択してCtrl+Cを押し、セルB1を選んでCtrl+Vを押してコピーができるか確認します。
Macの標準設定ではコピーにCommand+Cが割り当てられています。Ctrl+Cで操作したい場合はシステム環境設定の「キーボード>修飾キー」でControlキーとCommandキーを入れ替えてみてください。
Trackpadで右クリックやスクロールを快適にする
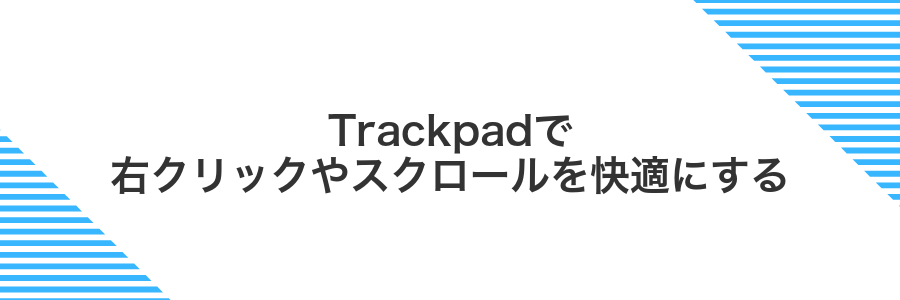
MacのTrackpadは魔法みたいに多彩なジェスチャーが使えるけど、Windowsのクリック感に慣れていると最初は戸惑います。右クリックを無理なく使えて、サクサクスクロールできるように設定しておけば、作業中にストレスフリーになれます。
- 副ボタンの登録:システム設定で二本指クリックやCtrl+クリックなど、自分らしい右クリック方法を選べます。
- スクロール方向の調整:慣れた上下移動のまま使いたいときは「ナチュラルスクロール」をオフにします。
- スクロール速度の微調整:同じ設定画面からトラックパッドの動きをゆっくり~速めまで好みの速さに合わせられます。
- 感度の最適化:ドラッグ中の誤動作を減らすために「トラッキング速度」を少しゆるめると安定します。
Trackpadの設定をほんの少し変えるだけで、Windowsライクな右クリックがすぐ手に馴染みますし、なめらかなスクロールは長文の確認やコード追いかけがグッと楽になります。
システム設定で副クリックをふた指タップに設定
画面左上のAppleメニューをクリックして「システム設定」を選びます。
サイドバーから「トラックパッド」をクリックして設定画面を表示します。
「副クリック」をオンにして、メニューから「ふた本の指でタップ」を選びます。
スクロール方向を自然にするか選び直す
画面左上のAppleマークをクリックしてシステム設定を開きます。
「トラックパッド」または「マウス」を選んで「スクロールの方向:自然」のスイッチを好みに応じてオン/オフにします。
BetterTouchToolでジェスチャーを追加する
BetterTouchToolを開くと、素早くジェスチャーを設定できる画面が表示されます。ここから指先の動きをあれこれカスタムできて、とても楽になるよ。
アプリを起動したらウインドウ左上の歯車アイコンをクリックして設定画面を表示します。
トラックパッドやマウスなどジェスチャーを追加したいデバイスを左側のリストからクリックします。
画面中央上にある+アイコンをクリックして、新しいジェスチャー行を追加します。
追加された行でプルダウンを開き、三本指スワイプやピンチインなど好みの動きを選びます。
その行の右側でウィンドウ移動やキーボードショートカット、AppleScriptなどを割り当てて保存します。
システム環境設定>セキュリティとプライバシーでトラックパッドやマウスの操作を許可しておかないと、ジェスチャーが反応しないので注意してください。
Homebrewで開発ツールを一括セットアップ
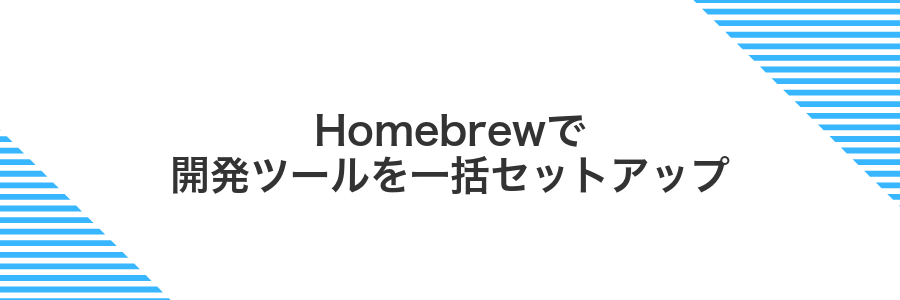
Homebrewは、Macで使うソフトや開発ツールをコマンド一発でまとめて入れられる魔法の箱のような仕組みです。Windowsで使っていたGitやNode.js、PythonなどもHomebrewひとつで一気に導入できるので、セットアップにかかる手間をグッと減らせます。
実際に使い始めると、Brewfileというリストに必要なパッケージを書き出しておくだけで、新しいMacでも同じ環境を瞬時に再現できるのがすごく便利でした。インストールやアップデートの管理が楽になるので、今後の開発がサクサク進みます。
エンジニア目線でのポイントとして、公式リポジトリにないツールはTap(外部リポジトリ)を追加しておくと安心です。これだけ押さえておけば、Homebrewでほとんどの開発環境をカバーできます。
ターミナルを開いてbrewをインストールする
Launchpadから「ターミナル」を探してクリックします。Spotlight(⌘+スペース)で「terminal」と入力しても起動できます。
ターミナルに以下のコマンドをコピー&ペーストしてEnterキーを押します。
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
brewfileを作ってよく使うアプリをまとめて入れる
Brewfileを使うと、よく使うアプリやパッケージをひとまとめに登録できて、新しいMacへ同じ環境をパパっと反映できます。
brew bundle dump --file=Brewfileで、インストール済みのHomebrewパッケージやCaskアプリがすべてBrewfileに記録されます。
プログラマー目線のコツとして、Brewfileの先頭に自分用のコメントを追加しておくと後から見やすくなります。
Brewfileを開いて、brew "wget"やcask "visual-studio-code"など、よく使うツールを追記してください。
個人的にはエディタやターミナルテーマ、フォントもここに登録しておくと、セットアップが楽になります。
brew bundle --file=Brewfileを実行すると、Brewfileに書かれたすべてのパッケージとアプリが自動でインストールされます。
作業が終わったらBrewfileをGit管理しておくと、将来の再セットアップがさらにスムーズになります。
brewupdateとbrewupgradeで最新を保つ
まずHomebrewのレシピ(パッケージ情報)をリモートから取得して最新状態にします。
初回や久しぶりに更新する場合は時間がかかることがありますが、完了すると次のアップグレードがスムーズになります。
brew update
続いて、ローカルにある古くなったツールやアプリを一気に最新版に切り替えます。
環境によっては複数のパッケージを更新するため時間がかかる点を覚えておくと安心です。
brew upgrade
brew upgrade中はCPUもディスクも使うので他作業を控えるとスムーズに終わります。
仮想化でWindowsもそのまま使う
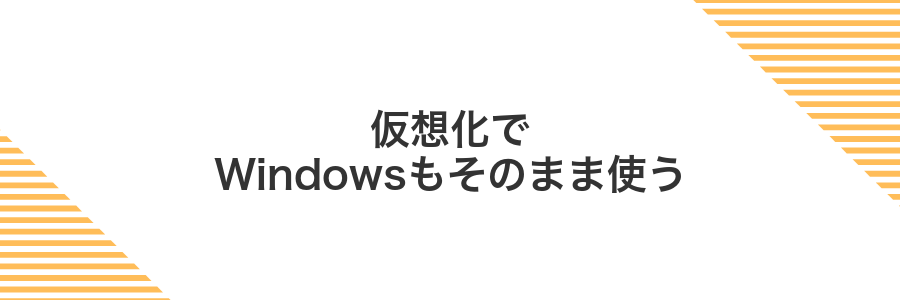
Windowsアプリをどうしても手放せないときは、仮想化ソフトが強い味方になります。Mac上にまるごとWindows環境を作り出して、再起動なしでmacOSとWindowsを行き来できます。
- 一緒に動かせる:macOSのデスクトップでそのままWindowsアプリを操作できるので、切り替えがスムーズです。
- コピー&ペースト共有:テキストや画像をWindows⇔Macで自由にコピペできて、資料作成や調べ物がはかどります。
- スナップショット機能:作業前に状態を丸ごと保存できるので、トラブルが起きてもすぐ元に戻せます。
AppleSiliconならParallelsをダウンロードする
お手持ちのブラウザでParallelsの公式サイトを開いてください。アクセス先はhttps://www.parallels.com/jp/です。
ダウンロードページでApple Silicon(M1/M2チップ)対応版を選んでください。無料体験版かライセンス版かを選ぶことができます。
選択後に表示されるダウンロードボタンをクリックすると、インストーラ(.dmgファイル)がダウンロードフォルダに保存されます。
ダウンロードした.dmgをダブルクリックで開き、表示されたParallelsアイコンをドラッグしてApplicationsフォルダにコピーします。これでインストールは完了です。
Windows11ARM版のイメージを取得してセットアップ
Appleシリコン搭載MacでWindowsを動かすにはARM版イメージが欠かせないよ。公式からISOを手に入れてUTMでさくっと仮想マシンを作ろう。
Windows Insider Programに無料登録しよう。開発版のARM64イメージ取得にアカウントが必要だから、このタイミングで済ませておくとスムーズだよ。
InsiderサイトのダウンロードページからWindows11 ARM64のISOを選んで入手しよう。大きめファイルだから安定したWi-Fiでダウンロードすると安心だよ。
UTMを起動して「新規作成」をクリック。ARM64 (aarch64)を選び、先ほどダウンロードしたISOをブートディスクに指定しよう。
仮想マシンを起動して通常のWindowsセットアップ画面が出るまで待とう。インストール先はデフォルトの仮想ドライブでOKだよ。
UTMのメモリ割り当てはホストの半分以下にすると過負荷を避けられるよ。
共有フォルダ設定でMacとファイルを行き来する
共有したいフォルダを右クリックしてプロパティを開き、共有タブで共有ボタンを押します。ユーザーを追加して< strong>読み書き権限を設定してください。
コントロールパネルのネットワークと共有センターからプライベートネットワークを選び、ネットワーク探索とファイル共有をオンにします。
Finderで移動メニューからサーバーへ接続を選び、“smb://WindowsのIPアドレス”を入力します。表示されたフォルダを選び、Windowsのユーザー名とパスワードを入れてマウントしてください。
つながった共有フォルダをFinderのサイドバーへドラッグするだけで、次回からワンクリックで開けるようになります。
同じWi-Fiネットワークに接続していないと、フォルダが見つからないことがあります。
よくある質問
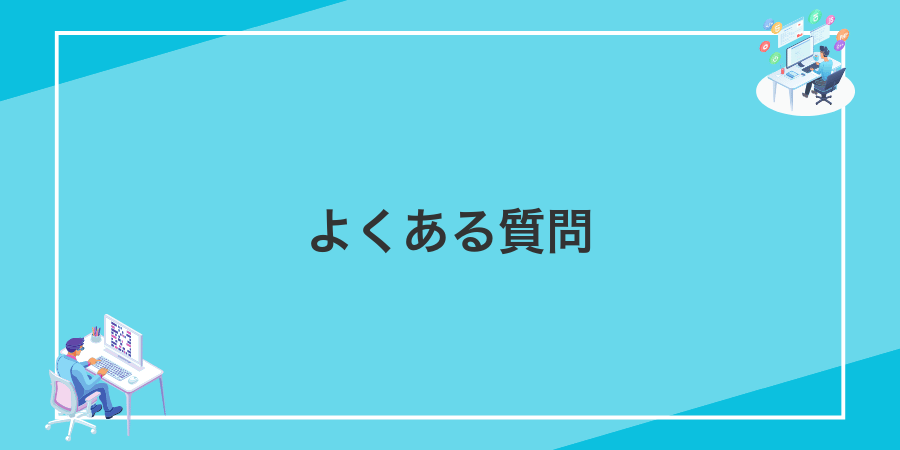
Windowsのデータと設定をMacにどうやって移せばいい?
- Windowsのデータと設定をMacにどうやって移せばいい?
移行アシスタントを使うと便利です。Windowsで「移行アシスタント」をインストールし、Macと同じネットワークにつなぎます。両方を起動して画面の指示に沿って進めるだけで、ユーザーフォルダやブラウザのブックマーク、メール設定までまとめてコピーできます。自宅Wi-Fiが遅いときは、有線LANアダプターを使うとスムーズです。
WindowsとMacでショートカットが違うと戸惑うんだけど?
- WindowsとMacでショートカットが違うと戸惑うんだけど?
CommandキーとControlキーの役割が逆なので最初は混乱します。Karabiner-Elementsというアプリでキーを入れ替えるとWindows感覚で使えます。慣れるまではショートカットリストを紙に貼っておくと安心です。プログラマー的にはよく使う操作だけカスタム登録しておくと効率が上がります。
Officeファイルの互換性って大丈夫?
- Officeファイルの互換性って大丈夫?
Microsoft365をMac版でインストールすればほぼ問題ありません。細かなレイアウト崩れが気になるときは、PowerPointならスライドマスターを使うと安定します。Linux系のオープンソースソフトを試すならLibreOfficeもありますが、プログラムのマクロなどは動作確認が必要です。
Windows用外付けHDDはそのままMacで読める?
Windows用外付けHDDをMacにそのまま繋いでも、まずはデータを読み込むことができます。
多くの場合、外付けHDDはNTFSやexFATでフォーマットされています。MacはNTFSを読み取り専用でサポートするので、ファイルをコピーしたり開いたりする分には問題ありません。
ただし、NTFSドライブにMacから書き込むには追加ツールが必要です。書き込みもスムーズに行いたい場合は、ファイルサイズの制限がなく幅広いOSで使えるexFATへ再フォーマットしておくと安心です。
移行アシスタントが途中で止まったときは?
移行アシスタントがピタッと止まるとドキッとしますよね。でも焦らずにちょこっとしたコツでスムーズに再開できます。
経験上、途中で止まる原因は大きなデータやネットワークの小さなズレだったりします。ここでは試してほしい方法をまとめました。どれも手順はシンプルなので、順番に確認してみてください。
- 移行アシスタントの再起動:MacとWindowsの両方でアプリを一度閉じてから再度立ち上げると、途切れポイントから続きを試せることが多いです。
- 有線接続に切り替え:Wi-Fiより安定するイーサネットケーブルやUSB-Cケーブルで直結すると、転送が途切れにくくなります。
- 外付けドライブ経由の転送:大容量の写真や動画だけ外付けHDDにまとめてコピーしてからMac側で読み込むと、移行アシスタントの負荷が軽くなります。
ざっくり確認してみるだけで、転送の途中停止からすぐに脱出できます。次のステップで具体的な手順を順番にご紹介しますので、ご安心ください。
OfficeライセンスはMacでも使える?
Officeのライセンス、Macでもそのまま使えるか気になりますよね。実際、Microsoft365のサブスクならWindowsでもMacでも同じアカウントでサインインするだけでさくっとアプリをダウンロードできます。
一方、一括購入のOffice2019やOffice2021はWindows専用だったりプラットフォームが限定されていることが多いです。手元にあるWindows版のプロダクトキーではMac版を認証できない場合があるので注意してください。
WindowsからMacへの乗り換えでOfficeを使いたいならMicrosoft365のサブスクがおすすめです。契約プランによって同時インストール台数が決まっているので、Macにも問題なくセットアップできます。
もしすでに一括購入版をお持ちの場合は、Microsoft公式サイトか正規販売店でMac版のライセンスを追加購入すると安心です。プログラマー視点で言うと、サブスクはバージョンアップの手間が省けて便利でした。
キーボード配列が違って戸惑うときの対処は?
Windowsで慣れ親しんだキー配置とMacのキー配列がちょっと違うと、コピペやショートカットで「あれ?」って戸惑うことがあります。特にCtrlキーとCommandキー、AltキーとOptionキーの位置が逆になると、無意識に誤操作を連発しがちです。
そんなときは、システム環境設定のキーボード>修飾キーから、使いたいキーを入れ替えてWindowsと同じ感覚にするのがおすすめです。それだけで普段のショートカット操作がスムーズになりますし、もっと細かく触りたい方はKarabiner-Elementsという無料ツールでキーを自在にカスタマイズすると、プログラミングやテキスト入力がぐっと快適になります。
Windowsで使っていたプリンターは繋がる?
Windowsで使っていたプリンターはUSB接続もWi-Fi接続もMacで動くケースがほとんどです。AirPrint対応機ならドライバを入れずにすぐ印刷できるので、とってもラクチンです。USB接続の場合でもメーカーのWebサイトからMac用ドライバをダウンロードすればあっという間に使えます。もしなかなか認識しないときは、Macに標準搭載されているCUPS(かっこ内:プリント管理システム)のWeb画面で設定すると意外とすんなり動きます。プログラマーならではの細かいカスタマイズもCUPSで挑戦できるので、好みに合わせて調整してみてください。
まとめ
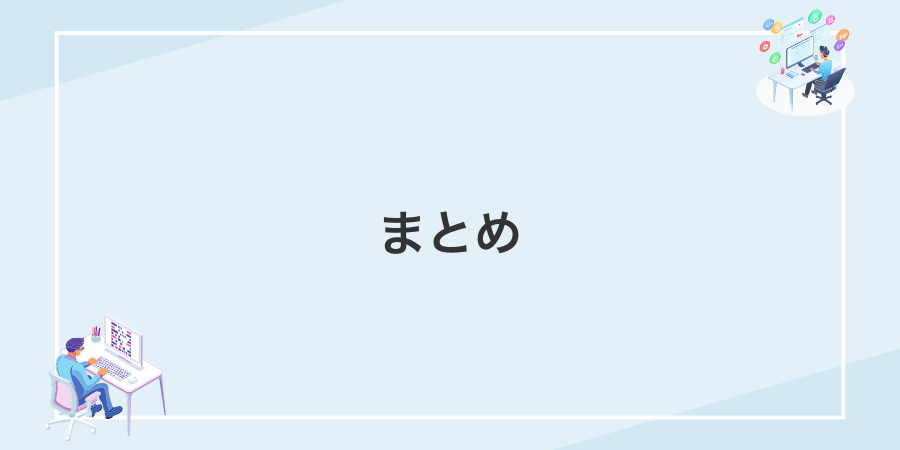
WindowsからMacへのお引越しは、事前のバックアップ→Macの「移行アシスタント」でデータ転送→アプリや設定の調整という3ステップでスムーズに完了します。それぞれをゆったり落ち着いて行えば、大切なファイルや使い慣れた環境をそのまま持ち込めるはずです。
あとはMacの心地よいインターフェースを楽しみながら、自分好みにカスタマイズする時間を満喫してください。使い込むほど便利な機能が次々と見つかりますから、気軽に遊びつつ新しい相棒にじっくり慣れていきましょう。