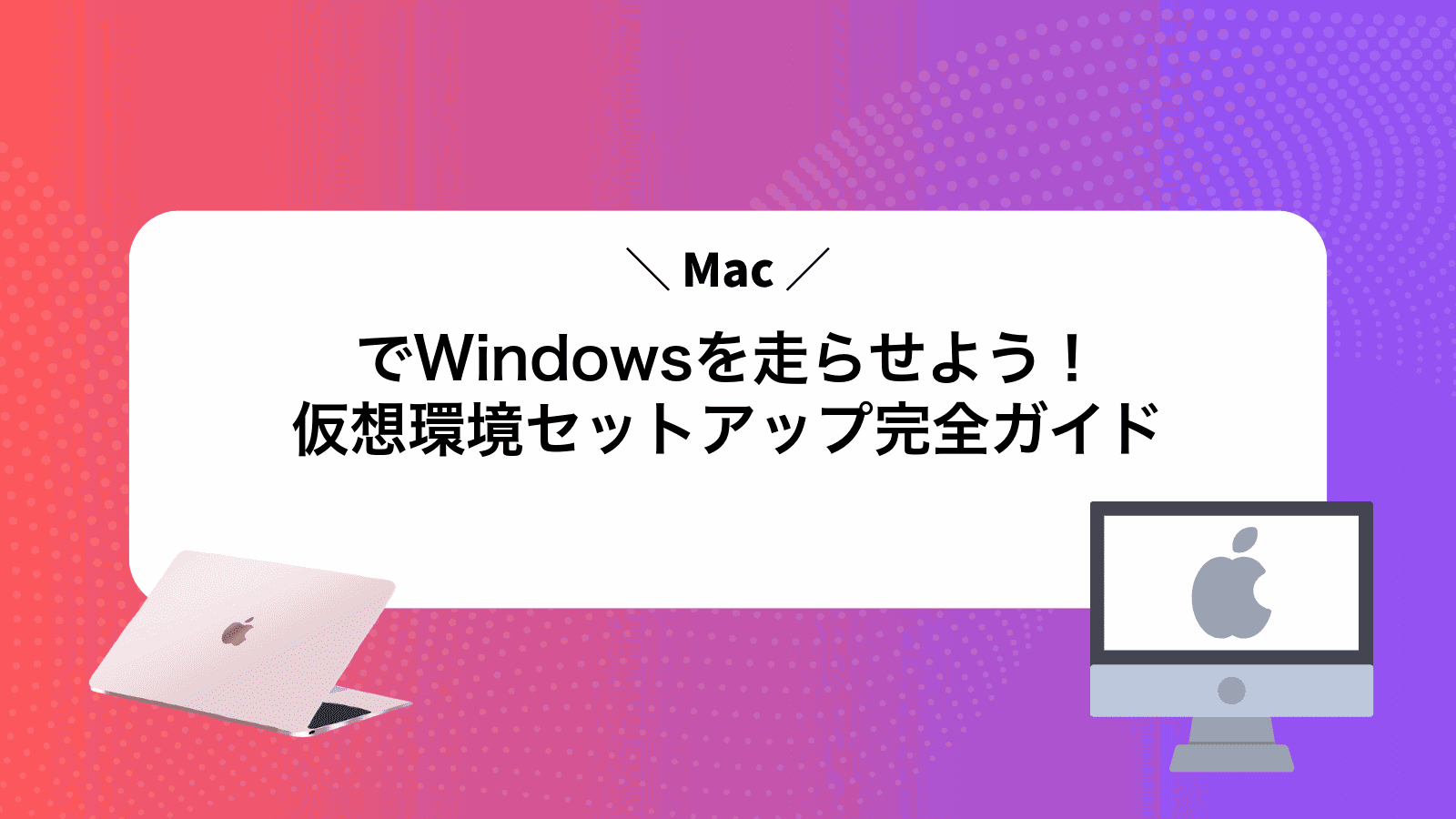Macを使い始めたものの、業務で必要なWindowsアプリを動かすための仮想環境がうまく整わず戸惑っていませんか?
ここでは、長年の開発現場で培った実践的な設定ノウハウをもとに、初めてでも迷わず進められる具体的な手順と、仕事を快適にする活用アイデアをお伝えします。そのため、追加の機材や複雑な操作に時間を取られることなく、MacとWindowsの両方の強みを同時に活かせます。
まずは基本のセットアップから取り組み、動く喜びを体験してください。そのまま応用も試せば、資料作成と開発を行き来しても作業が途切れず、毎日のパフォーマンスが軽やかに向上します。
MacでWindows仮想環境を作る具体的な手順
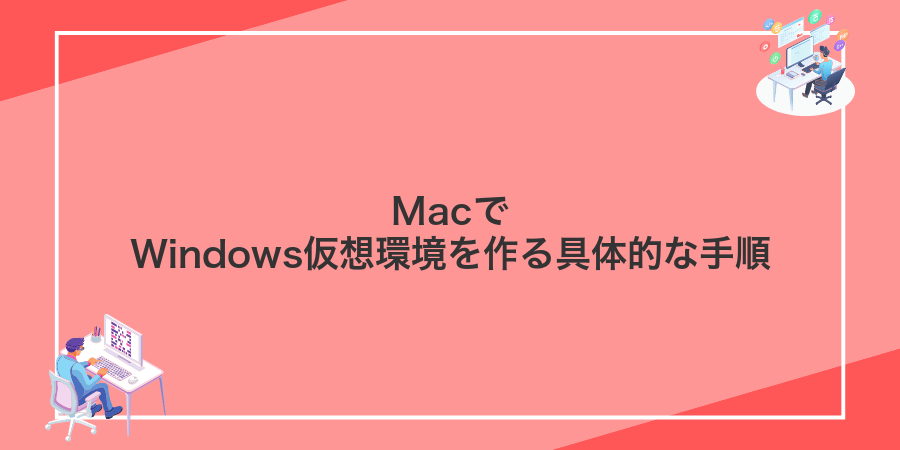
MacでWindowsを動かすには仮想環境ソフトが便利です。初めてでも扱いやすいツールを選べば、Macから離れずにWindowsアプリをサクサク動かせます。
- Parallels Desktop:インストールが簡単でドラッグ&ドロップでファイル共有もシームレス
- VMware Fusion:企業での導入実績が豊富で安定感が高い
- VirtualBox:無料で日本語化も可能なのでコストを抑えたい人向け
どれも魅力がありますが、自宅の勉強用途ならVirtualBox、業務でがっつり使うならParallels DesktopやVMware Fusionが安心です。
- 仮想マシンのメモリはMac全体の半分以下に抑えてホストを快適に保つ
- スナップショットは必ず有効にしてトラブル時にすぐ戻れるようにする
- ネットワーク設定は「共有」にするとMacとWindowsでファイルやプリンタ共有が楽になる
まずは自分の用途や予算に合わせてソフトを決めるところから始めましょう。準備が整ったら、次はインストールとWindowsイメージの読み込みに進んでいきます。
ParallelsDesktopで一番かんたんに始める

Parallels Desktopは、Mac歴10年のわくわくするような体験をそのまま仮想環境に持ち込める、らくらくスタートな一押しツールです。
インストーラーをポチッと起動するだけで、Windows ISOの自動ダウンロードから仮想マシンの作成までが画面の案内に沿ってスイスイ進みます。起動後はmacOSとWindowsの間でドラッグ&ドロップやコピー&ペーストがストレスフリーに使えます。
- ワンクリックセットアップ:面倒な設定やコマンド不要でサクッと始められる
- シームレス共有:ファイルやクリップボードをOS間で直感的にやり取りできる
- Apple Mチップ対応:M1/M2チップ搭載Mac上でも高速かつ安定動作する
「難しそう」と感じる瞬間が一切なく、まるでMacのアプリを増やす感覚でWindowsの世界が手に入ります。これから仮想環境を初めて触る人にも、迷わずおすすめできる楽しさがあります。
①ParallelsDesktop公式サイトへアクセスしてトライアルをダウンロードする
まずはParallelsDesktopの公式サイトにアクセスして、無料トライアルを手に入れましょう。ブラウザでURLを入力するだけで、すぐにダウンロード画面にたどり着けます。
SafariやChromeで「parallels desktop トライアル」と検索し、一番上に出てくる公式ページをクリックします。
「無料トライアルをダウンロード」というボタンをクリックし、メールアドレスを入力するとすぐに.dmgファイルがダウンロードされます。
ダウンロードファイルは約500MBと大きめなので、安定したWi-Fi環境で進めると安心です。
②ダウンロードしたdmgを開きアイコンをドラッグしてインストールする
ダウンロードフォルダにあるdmgファイルをダブルクリックしてマウントします。デスクトップにディスクが現れるのを確認してください。
表示されたウインドウ内でアプリのアイコンをApplicationsフォルダにドラッグ&ドロップします。
コピーが終わったら、Finderのサイドバーでマウントしたディスクを右クリックして「取り出す」を選んでください。
セキュリティ設定により初回は「開発元未確認アプリ」と表示される場合があります。その場合はアプリアイコンを右クリックして「開く」を選び、承認してください。
③初回起動でWindows11ダウンロードを選び自動セットアップを待つ
初回起動すると自動でWindowsインストールのウィザードが立ち上がります。画面に表示されるWindows11をダウンロードをクリックして、ダウンロードをスタートしてください。
ダウンロードサイズは約5GBあるため、お使いの回線速度に応じて10分~30分ほどかかります。進捗バーが出るので完了するまで静かに待ちましょう。
ネット回線が途中で切れないように、可能なら有線LAN接続を使うとスムーズです。Macのスリープ設定もオフにしておくと安心です。
④完了画面で「仮想マシンを起動」をクリックしてWindowsを確認する
セットアップが終わると表示される完了画面で「仮想マシンを起動」をクリックします。
数秒後にWindowsのロゴが表示されるので、無事に立ち上がったことを確認しましょう。
もし何も起きないときは、メニューの仮想マシン一覧から対象を選び「起動」を押すと解決することがあります。
初回起動はディスク構成などの初期化に時間がかかることがあるので、焦らず待ってみてください。
⑤「共有フォルダ」ウィザードでMacの書類フォルダを追加する
Windows仮想マシンを起動して画面上部の「デバイス」メニューから「共有フォルダ」→「共有フォルダの設定」を選択します。
ウィザード画面の右にある「フォルダ追加」ボタン(+)をクリックし、ポップアップで「フォルダーのパス」にMacのホーム配下にある「書類」を指定します。「フォルダ名」は「Documents」など分かりやすい名前を入力し、「自動マウント」にチェックを入れてOKを押します。
VMwareFusionPlayerでコストゼロの選択肢

VMwareFusion Playerは個人利用なら無料で使える仮想環境ソフトです。macOSとの相性もよくて、Windowsのインストールや起動も直感的に進められます。
- コストゼロ:個人利用向けライセンスが無料なので追加費用なしでスタートできます。
- 高い互換性:最新のmacOS VenturaやWindows11にも対応しているので安心できます。
- スナップショット:設定変更前に状態を保存できるから失敗してもすぐ戻せて頼もしいです。
①VMware公式サイトからPersonalUseライセンスキーを取得する
WebブラウザでVMware公式サイトにアクセスし、画面右上のサインインからアカウントへログインします。
メニューの「ライセンス&ダウンロード」ページを開き、PersonalUseライセンス欄までスクロールします。
「ライセンスキーを取得」ボタンをクリックするとキーが表示されるので、コピーしてテキストエディタなどに貼り付けて安全な場所へ保存しておきます。
②ダウンロードしたインストーラpkgを実行し指示どおりに進める
DockやFinderのサイドバーからDownloadsフォルダをクリックして、ダウンロードした.pkgファイルを表示します。
インストーラのアイコンをダブルクリックすると、macOSのインストーラが起動します。
画面の「続ける」ボタンをクリックし、使用許諾に同意して先へ進めます。
インストール先のディスクを選んで「インストール」を押し、Macの管理者アカウントのパスワードを入力します。
インストールが終わったら「閉じる」ボタンを押し、アプリケーションフォルダでソフトを確認しましょう。
.pkgの実行時に「開発元を確認できません」と表示されたら、システム環境設定>セキュリティとプライバシー>一般タブで「このまま開く」をクリックして許可してください。
③新規仮想マシン作成をクリックしWindowsISOを選択する
Parallels Desktopの画面で新規仮想マシン作成ボタンを押します。
続いてファイル選択ダイアログが開くので、あらかじめダウンロードしておいたWindowsのISOイメージを指定してください。
ISOはデスクトップや「ダウンロード」フォルダにまとめておくと、あとから見つけやすくなります。
ISOファイルはMicrosoft公式サイトから取得した最新バージョンを選ぶと安心です。
④「簡易インストール」を有効にしてキーボードレイアウトを選ぶ
仮想マシンの設定画面で「簡易インストール」にチェックを入れます。そのあと表示されるプルダウンから使いたいキーボードレイアウトを選択します。日本語環境なら「Japanese-日本語」を、英語配列を使いたいときは「US」を選ぶと入力トラブルが少なくて安心です。インストール後にレイアウトが違うとパスワード入力時にうまく文字が出ず焦りがちなので、この設定は必ず確認してください。
英語キーボード扱いにしていると「@」や「”」の位置が国内配列と異なる点は要注意です。
⑤完了後にVMwareToolsをインストールして表示解像度を最適化する
VMware Fusionのメニューバーで仮想マシンを選び「VMware Toolsをインストール」をクリックします。自動でWindows上に仮想CDがマウントされます。
エクスプローラーで新しいドライブを開き「setup.exe」を右クリックして「管理者として実行」を選びます。これで必要なドライバが自動でインストールされます。
表示されるウィザードで「次へ」をクリックし続けてインストールします。途中画面の解像度変更オプションは標準設定のままで問題ありません。
インストール完了後に表示されるメッセージで再起動を実行します。再起動後に高解像度でWindowsが表示されているか確認してください。
VirtualBoxで全部無料で始める
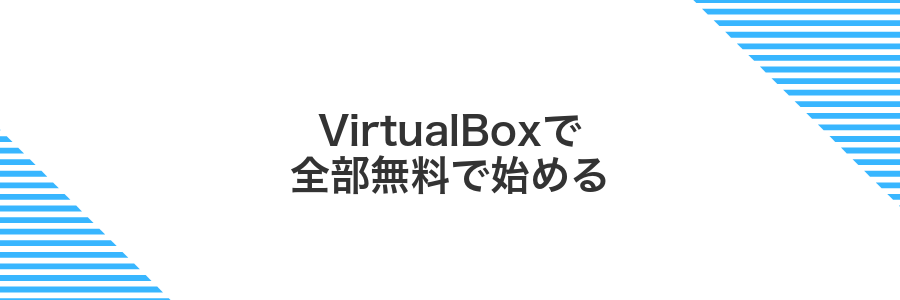
VirtualBoxはオラクルが提供する無料の仮想環境ソフトです。Mac上でWindowsをはじめさまざまなOSを動かせるうえ、ライセンス料が一切かかりません。
インストールや初期設定はウィザード形式で進むため、初めて仮想マシンを触る人でも迷わず進められます。メモリやストレージの割り当てもあとから柔軟に調整できるのがうれしいポイントです。
コストをかけずにWindows環境を試したいときや、ちょっとした動作確認用のサンドボックスがほしいときにぴったりの選択肢です。
①VirtualBoxと拡張パックを公式サイトからダウンロードする
お好みのブラウザで公式ダウンロードページにアクセスします。https://www.virtualbox.org/wiki/DownloadsというURLです。
「VirtualBox x.x.x platform packages」欄から、利用中のMacのアーキテクチャに合ったmacOS用インストーラーを選んでダウンロードします。Intel版なら「macOS (x86/64)」、Apple Siliconなら「macOS (Arm64)」です。
同じページの「VirtualBox x.x.x Oracle VM VirtualBox Extension Pack」リンクから拡張パックをダウンロードします。こちらは「All supported platforms」を選べばOKです。
インストーラーと拡張パックはバージョンを必ず揃えてください。ずれるとあとで取り込めないことがあります。
②dmgを開きVirtualBox.pkgを実行しセキュリティ許可を行う
ダウンロードした「VirtualBox-7.x.x.dmg」をダブルクリックしてマウントします。
マウントされたディスクイメージ内にある「VirtualBox.pkg」をダブルクリックしてインストーラーを起動します。
インストール開始時に「開発元を検証できませんでした」といった警告が出た場合は、一度インストーラーを閉じてからシステム設定で許可を行います。
Appleメニューからシステム設定を開き、「プライバシーとセキュリティ」の「一般」欄にある「Oracle America, Inc.のシステムソフトウェアの読み込みを許可」をクリックしてください。
許可が終わったら再度「VirtualBox.pkg」をダブルクリックすると問題なくインストールが進みます。
③「新規」ボタンをクリックしWindows11を選択してメモリを4GB以上に設定する
仮想マシン管理画面で新規をクリックしたら表示されるOS一覧からWindows11を選びます。
続いてメモリ設定に移り4GB以上を割り当ててください。余裕をもたせるなら6GB以上がおすすめです。
メモリが足りないとインストール時に止まったり動作が遅くなるので注意してください。
④仮想ディスクをVDI方式で作成しサイズを動的割り当てにする
ディスクの種類を選ぶ画面でVDI(VirtualBox Disk Image)を指定します。これはVirtualBox純正のフォーマットなので互換性が高く、あとで管理しやすいですよ。
次にストレージの割り当て方法は可変割り当て(動的割り当て)を選びます。これだと最初は小さなファイルから始まり、ゲストOSがデータを増やすに連れてホスト側のディスクを使って少しずつ大きくなります。
仮想ディスクの容量は50GB前後を目安に。足りなくなっても後からリサイズできるので気軽に決めてください。動的割り当てならホストの空き領域を無駄なく使えるので、ストレージに余裕がないときにも安心です。
⑤設定メニューで「共有フォルダー」を追加しオートマウントをオンにする
仮想マシンを停止した状態で、VirtualBoxのウィンドウから該当するWindowsを選びます。上部メニューの「設定」をクリックしてください。
「共有フォルダー」タブを開き、「+(追加)」ボタンを押します。ホストのフォルダー欄でMac側のディレクトリを指定し、名前を任意に設定します。「オートマウント」にチェックを入れて「OK」を押しましょう。
この設定後はWindowsを再起動すると、エクスプローラーの「ネットワークドライブ」に共有フォルダーが自動でマウントされます。
Windows仮想環境で毎日がもっと便利になる応用ワザ
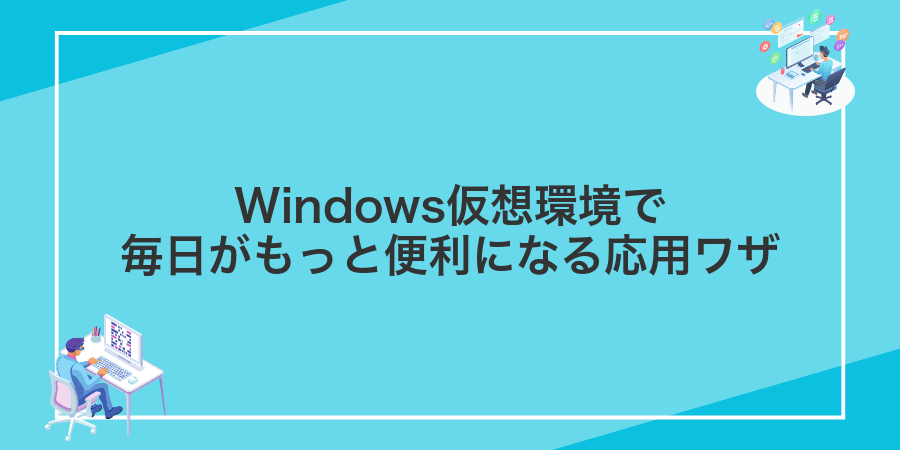
Windows仮想環境を使い倒すと、ちょっとした工夫で毎日の作業が楽しくなります。ここではプログラマー視点でおすすめの応用ワザをまとめました。
| 応用ワザ | 活用シーン | 役立つポイント |
|---|---|---|
| クリップボード共有設定 | Mac⇔Windows間でテキストや画像を移動 | コピー&ペーストがスムーズになり手間が減る |
| 共有フォルダ活用 | ファイルを頻繁にやり取りするとき | ドラッグ&ドロップで簡単にファイル共有できる |
| スナップショット運用 | 設定を試したりソフトをテストするとき | いつでも元の状態に戻せるので安心して試せる |
| 仮想デスクトップ切り替え | マルチタスクで複数ウィンドウを整理するとき | 作業ごとにデスクトップを分けて集中しやすくなる |
| リモート接続の活用 | 外出先から自宅の環境へアクセスするとき | 手元の環境をそのまま使えて開発が止まらない |
MacとWindows間でドラッグ&ドロップ共有
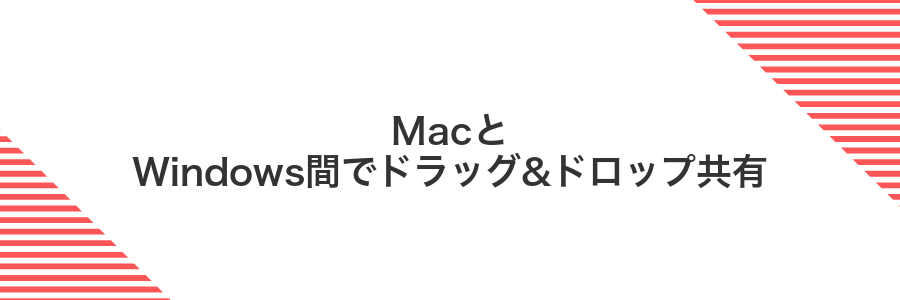
MacのデスクトップからWindows仮想マシンのウィンドウにファイルをドラッグ&ドロップするだけで、自動的に中身が共有されます。仮想環境に必要なツール(Parallels ToolsやVMware Toolsなど)が入っていれば、特別な設定なしで直感的に操作できるのが魅力です。
- 手軽さ:普段のドラッグ&ドロップ操作そのままなので覚える必要なし
- 高速性:大容量でなければ即座に共有が完了
- 互換性:ParallelsもVMwareもVirtualBoxも専用ツール導入で利用可能
共有フォルダを設定してファイルをすぐ渡す
仮想環境のメニューから「共有フォルダ」もしくは「Shared Folders」を開きます。Parallelsなら画面上部の歯車アイコン→「オプション」→「共有」、VirtualBoxならメインウィンドウの「設定」→「共有フォルダー」です。
「+」ボタンでMac上の任意のフォルダを選び、Windows側にマウントするパスを指定します。自動マウントをオンにすると、次回起動時から自動でドライブ割り当てされるので便利です。
Windowsを起動後、エクスプローラーを開いて「ネットワーク」→「VBOXSVR」や「\\Mac\username」などにアクセスすると、先ほど指定したフォルダが見えます。そのままドラッグ&ドロップでファイルのやり取りができます。
Windows側のファイアウォールやネットワーク設定でアクセスできないことがあるので、その場合は仮想マシンツールの拡張機能(Guest AdditionsやParallels Tools)の再インストールを試してください。
コピー&ペースト共有を有効にしてテキストをシームレスに扱う
Windowsを起動したままVirtualBoxのメニューからデバイス>Guest Additions CDイメージの挿入を選んでください。
エクスプローラーで「VBox Windows Additions」ドライブを開き、Setup.exeをダブルクリックでインストールを進めます。
VirtualBoxアプリで対象VMを選び、設定>一般>詳細タブの共有クリップボードを双方向に切り替えます。
Windows内のセキュリティ警告が出たら「許可」をクリックしてください
スナップショットで安全テスト
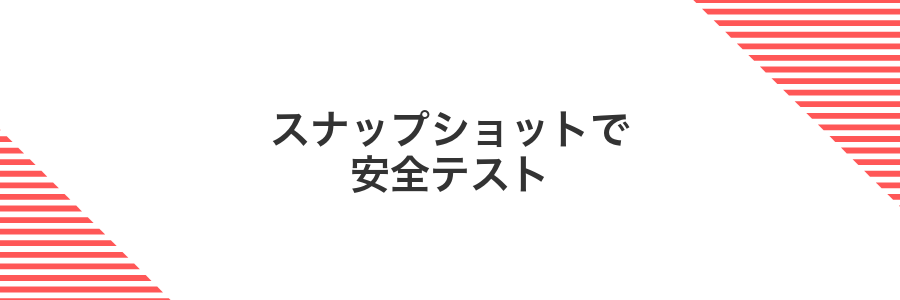
Windowsをいじっていると「この設定で大丈夫かな?」と不安になることがありますよね。スナップショットがあれば、まさにその瞬間のマシンの状態をまるごと記録できるので、あとからすぐに元の状態に戻せます。
- 安心してテストできる:失敗しても記録時点にワンクリックで戻せます。
- 設定を気軽に変更:レジストリやドライバを試してみたいときも怖くありません。
- トラブルシュートにも便利:動作がおかしくなったら、原因を追いやすい状態に戻して何度でもチャレンジできます。
新しいスナップショットを作成して実験前の状態を残す
仮想マシンがシャットダウンされていることを確認してから、VirtualBoxのメイン画面で対象のVMをクリックします。
上部メニューのスナップショットタブを選び、左下のカメラアイコンをクリックして「新規スナップショットを作成」を選択します。
ポップアップで名前(例:BeforeUpdate_2024-06-30)と任意の説明を入力し、作成を押してください。
スナップショットはディスク容量を消費します。実験が終わったら古いものを整理しましょう。
不要になったスナップショットを削除して容量を節約する
不要になったスナップショットを消して、仮想マシンのディスク容量をすっきり節約しましょう。
VirtualBoxの場合はウィンドウ右上の×アイコンで終了、Parallelsならメニューの「仮想マシンを停止」を選んで確実にシャットダウンします。
VirtualBoxなら左サイドの仮想マシンを選んで上部の「スナップショット」タブへ。Parallelsでもコントロールセンターから「スナップショット」をクリックします。
一覧から不要な名前を選び、ゴミ箱アイコンや右クリックの「削除」を押します。
CLIならVBoxManage snapshot "vm名" delete "スナップ名"で消せます。
スナップショットを消すと元に戻せません。削除前に必要な状態かどうかよく確認してください。
ゲームも快適!フルスクリーンとGPU支援の設定
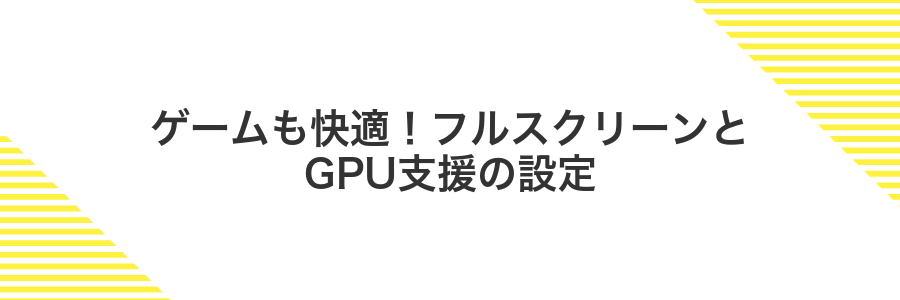
Windowsの仮想環境で本格ゲームを楽しみたいなら、フルスクリーンとGPU支援の設定は欠かせません。
Parallels DesktopやVMware Fusionなら、仮想マシンの設定画面でワンクリックでGPU支援を有効化できます。MacのGPUリソースを直接活用できるので、グラフィック負荷の高いタイトルもカクつきなく動かせます。
さらにフルスクリーンにすると、WindowsとMacの解像度がぴったり合って、ディスプレイ領域をまるごと使えるようになります。まるでWindowsマシンをそのまま使っているかのような没入感が手に入ります。
ポイントはグラフィックメモリを多めに割り当てることと、仮想マシンの画面設定で解像度をMac本体と同じにそろえることです。これだけでラグを抑えた快適プレイが実現します。
仮想マシン設定で3Dアクセラレーションをオンにする
3Dアクセラレーションを有効にするとWindowsの描画が滑らかになり動画再生やUI操作がより快適になります。
DockやアプリケーションフォルダからVirtualBoxを開き、サイドバーにある対象のWindows仮想マシンをクリックします。
画面上部の歯車アイコンをクリックし、「ディスプレイ」タブを選択します。
「ハードウェアアクセラレーション」セクションにある3Dアクセラレーションを有効化のチェックボックスにチェックを入れます。
同じ画面でビデオメモリのスライダーを右端まで移動し、推奨値まで割り当てておきます。
フルスクリーンモードを切り替えて遅延を減らす
仮想環境をウィンドウモードで使うと、Macのウィンドウ管理やデスクトップエフェクトが邪魔をして操作や画面表示に遅れが出やすくなります。フルスクリーンに切り替えると、仮想マシンが画面全体を専有してMac側の余計な処理を減らせるので、操作感がぐっと軽くなります。
仮想マシンのメニューバーから「表示」→「フルスクリーンを切り替え」を選ぶか、Control+Command+Fを押して全画面表示にします。
仮想マシンの設定で「Retina対応(高DPI)を有効化」や「表示スケールを100%」に切り替えて、無駄なスケーリング処理をなくします。
フルスクリーン中はメニューバーやDockが隠れるので、ショートカットキーで切り替えないと戻せない点に気をつけてください。
自動起動と停止で作業を時短
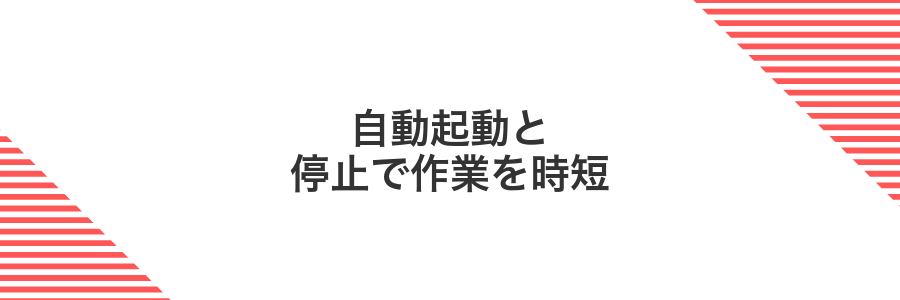
Windowsを起動するたびにアプリを立ち上げたりシャットダウンを待ったりしていると、何度も同じ手間がかかってうんざりしますよね。仮想マシンの自動起動と自動停止を設定すれば、Macの電源を入れた瞬間にWindowsが裏で立ち上がり、終了時にはきれいにシャットダウンしてくれるので、煩わしい操作をぐっと減らせます。
Parallels Desktopなら設定画面で「Mac起動時にこの仮想マシンを自動で開始」を有効にするだけで手間いらずです。VirtualBoxを使っている場合は、macOSのlaunchdやシェルスクリプトを使って起動・停止スクリプトを登録すると、コマンド一発で同じように扱えます。毎日の作業がサクサク進むので、時間を大切にしたい人ほど試してみてほしい機能です。
Macログイン時にWindowsを自動起動に設定する
アップルメニューから「システム環境設定」を開き、「ユーザとグループ」を選びます。現在のアカウントを選択したらログイン項目タブをクリックし、+ボタンでアプリケーションフォルダからParallels Desktop.appを追加します。
Parallels Desktopを起動し、仮想マシンリストで対象のWindowsを右クリックして「構成」を選びます。一般タブ内で「Macログイン時に自動的に開始」にチェックを入れると、次回からMacログイン時にWindowsが自動で立ち上がります。
Parallels Desktopをログイン項目に追加するときは、仮想マシンを完全にシャットダウンしておくのがおすすめです。
Macの終了に合わせて仮想マシンを自動停止する
Parallels Desktopを起動して、メニューバーからParallels Desktop>環境設定…を選びます。
環境設定の全般タブを開き、Mac終了時のプルダウンから仮想マシンを停止を選びます。
ウインドウを閉じると設定が自動で保存されます。次回Macを終了すると、自動で仮想マシンが停止します。
仮想マシンを停止するときは、保存していないファイルが失われる可能性があるので、終了前にWindows側で作業内容を保存してください。
よくある質問
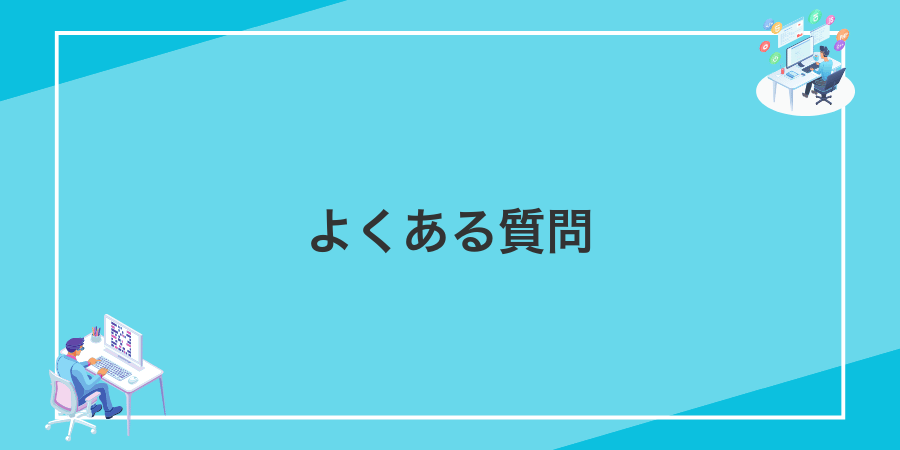
M1/M2 MacでもWindows11を動かせますか?
- M1/M2 MacでもWindows11を動かせますか?
Parallels Desktop 18を使えばAppleシリコン搭載のMac上でWindows11 ARM版が快適に動きます。仮想化対応のInsider PreviewイメージをParallelsに読み込むだけでOKです。VirtualBoxや旧バージョンのParallelsではARM版に対応していないのでご注意ください。
仮想環境の動作はネイティブに近いですか?
- 仮想環境の動作はネイティブに近いですか?
Parallelsの場合はCPUやGPUのアクセラレーションを直接活用できるので、軽い開発用途ならほぼネイティブと遜色ありません。メモリやCPUコアを多めに割り当て、仮想ディスクをSSDに配置することでさらに快適になります。
Windowsライセンスは必要ですか?
- Windowsライセンスは必要ですか?
試用なら無償のInsider Preview版で数日から数週間動かせますが、長期利用や商用利用には正規のプロダクトキーが必要です。Microsoftストアや大手家電量販店で購入したキーをParallelsの設定画面に入力すると有効化できます。
MacとWindows間のファイル共有はどうすればいいですか?
- MacとWindows間のファイル共有はどうすればいいですか?
ParallelsならVM設定→オプション→共有からMacのフォルダを追加できます。Windows側では共有ドライブがエクスプローラーに表示されるので、ドラッグ&ドロップでシームレスにやり取りできます。
IntelMacとAppleSiliconで手順は変わる?
Intel搭載のMacは、従来から広く使われてきたx86アプリと相性が良く、Parallels DesktopやVMware Fusionでのセットアップがとってもスムーズです。
AppleSilicon(M1/M2)はARMアーキテクチャなので、WindowsはARM版を利用する必要があります。Parallels Desktop for Mac(AppleSilicon対応版)やUTMなどでARM版Windowsを動かせるものの、x86ネイティブ向けアプリを使うときはエミュレーション越しになる点に注意してください。
ざっくりまとめると、IntelMacならx86版Windowsで幅広いソフトが快適に動きやすいですし、AppleSiliconは省電力で静かに動くのが魅力ですがARM対応アプリを選ぶ場合や、x86向けアプリをエミュレートする分だけパフォーマンスが落ちる点を意識すると安心です。
Windowsライセンスは別途必須?
Windowsを仮想環境で動かすには、正規のWindowsライセンスが別途必要になります。Parallels Desktopには90日間使える試用版があるのでまずは雰囲気をつかむのに便利ですが、長く使うならライセンス取得を忘れずに行ってください。
個人的にはMicrosoft Storeでデジタルライセンスを購入するのがお手軽でおすすめです。格安キーを扱うショップもありますが、信頼性を重視するなら公式ストアからの購入が安心感があります。
ParallelsとVMwareどちらが軽い?
ParallelsとVMwareどちらが軽いか気になるよね。手持ちのMacBookAir M2で試してみたところParallels Desktopを動かすとメモリ使用量がだいたい2GB前後なのに対してVMware Fusionは3GB近く使うことが多かった。CPUがアイドル状態でもParallelsはほんのわずかな負荷しかかけないから、バッテリーの持ちも良くて助かっている。
サクッとWindowsを立ち上げたいならParallelsのほうが頼もしい感じ。一方でVMwareの設定にすでに慣れていたり、チームでVMwareを使い回しているなら少し重めでもこちらを選んだほうが扱いやすいかも。とにかく軽さ重視ならParallels、なじみ重視ならVMwareという感じで使い分けるといいよ。
Macが重くなったときの対処は?
- Macが重くなったときの対処は?
-
まずは起動中のアプリを見直して不要なものを終了しましょう。特にブラウザでタブが大量に開いているとメモリを大きく使います。アクティビティモニタでCPUやメモリの負荷が高いアプリを見つけて対応してください。次にWindows仮想マシンに割り当てるメモリ量を調整し、macOS側にも十分な余裕を持たせると動作が安定します。搭載メモリが少ない場合はアプリの同時起動数を減らすか、増設できるモデルならメモリ追加を検討すると快適に使えます。ストレージがHDDならSSDに換装すると全体の動きがぐっと軽くなります。
BootCampとの違いは?
BootCampはmacOSとWindowsを切り替えて起動する方式でWindowsをネイティブ動作させられるため重いグラフィック処理やゲーム向けにぴったりです。ただし切り替え時に再起動が必要になり作業の合間にサクッと移行しづらい点があります。
一方仮想環境はParallelsDesktopやVMwareFusionを使いmacOS上でWindowsを同時起動できるためアプリ間のファイル共有やコピー&ペーストがとても楽です。若干のパフォーマンス差はありますがプログラミングやオフィス作業程度ならまったく問題ありません。
それぞれの特徴を把握して用途に合わせて選ぶと操作性の快適さをさらに実感できます。
仮想環境でウイルス対策は必要?
仮想環境はホストのOSからある程度独立しているため「ウイルスが入りにくいんじゃない?」と思いがちです。確かに物理マシンよりリスクは下がりますが、まったく安全というわけではありません。
ゲストOSでダウンロードしたファイルやネットワーク越しに持ち込まれるウイルスは、ゲスト内で動作します。さらにゲストからホストへファイル共有してしまうと、思わぬタイミングでホスト側にも感染が広がることがあります。
そこでゲストOSにも軽量のウイルス対策ソフトを入れるのがおすすめです。実際にいくつか試したところ、メモリやCPUへの負荷が低いツールを選べば、開発作業にほとんど影響なく安全性を高められました。
| 対策 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| ホストのみ設置 | 設定が一度で済む | ゲスト内感染に気づきにくい |
| ゲストOSにも設置 | ウイルス検知率アップ | わずかなリソース消費 |
| サンドボックス利用 | 実行ファイルを隔離 | 手順が増える |
ウイルス対策をきちんと入れておけば、安心して開発や検証に集中できます。ゲストOSで問題が出たときも、すぐに検知・隔離できるので慌てずにすみました。
まとめ
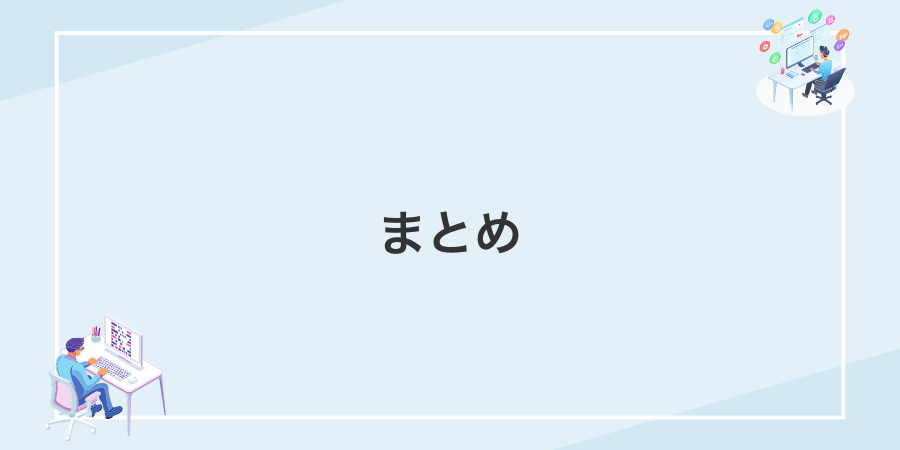
仮想化ソフトのインストール、Windows ISOイメージのダウンロード、仮想マシンの作成と基本設定、そしてWindows起動後のドライバ導入を順に進めるだけで、Mac上に快適なWindows環境が整います。
これでWindows専用ソフトやゲームも難なく動かせるようになります。時間があるときにスナップショット機能でバックアップを取ったり、共有フォルダを設定してファイルのやり取りをもっと楽にしてみてください。さっそく仮想環境ライフを楽しみましょう。