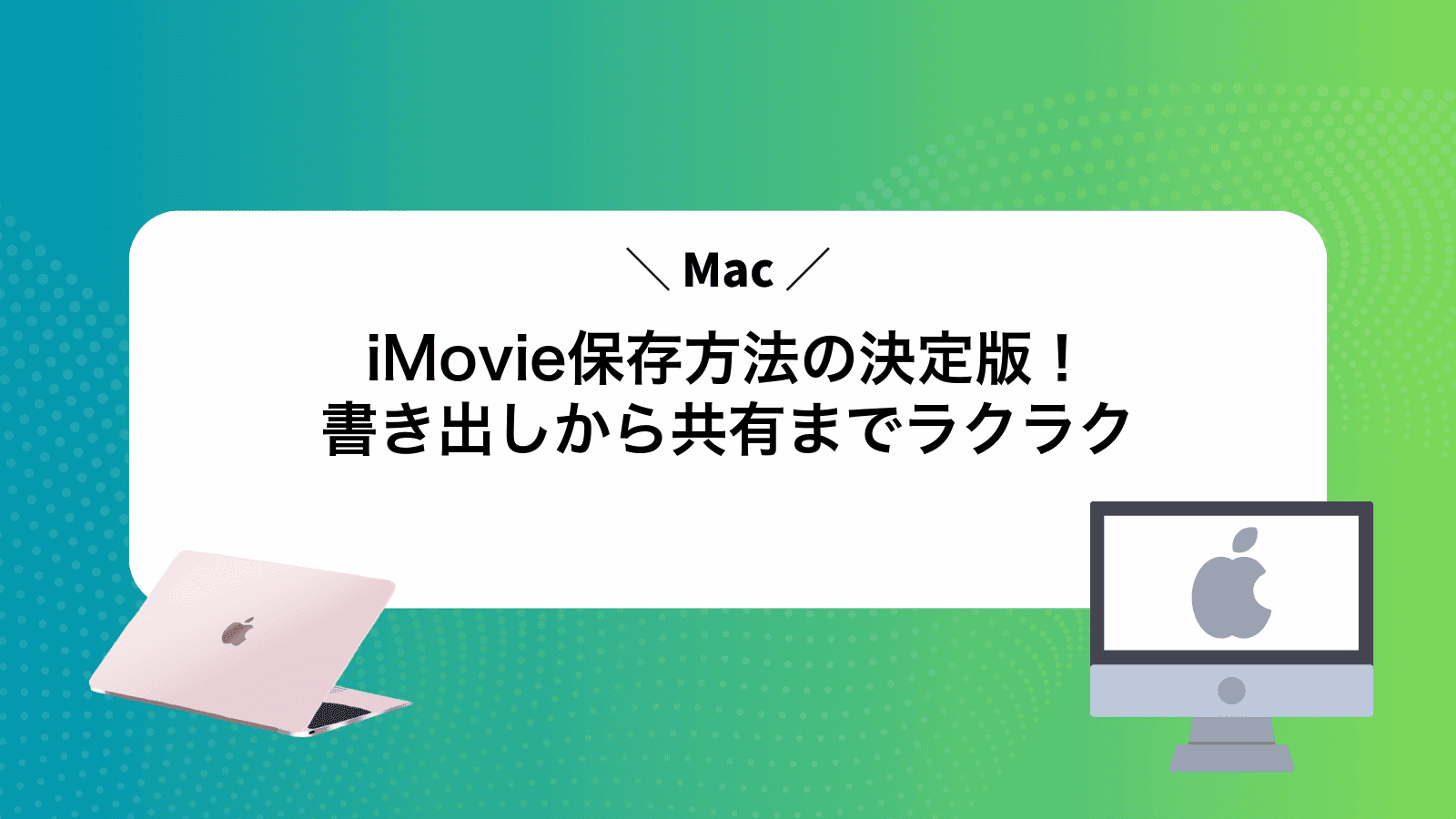iMovieで作った動画をいざ家族に見せようとしたとき、保存方法が分からずにプロジェクト画面で手が止まってしまうことはありませんか?
ここではメニュー操作の細かなクリック位置からファイル形式選択のコツ、さらに書き出し中に進捗を倍速で終わらせるプログラマー流の裏ワザまで、実体験をもとに迷わず進める手順をまとめています。オフラインでも安心なバックアップの取り方や容量を抑える圧縮設定も紹介し、完成動画をすぐ共有できる状態へ導きます。
画面を開きながら順番どおりに進めるだけで、予期せぬエラーやサイズ超過に悩まされる時間がぐっと減ります。さっそくプロジェクトを用意して、一緒にスムーズな書き出し体験を始めてみてください。
iMovieで動画を保存する手順をゼロからていねいに紹介
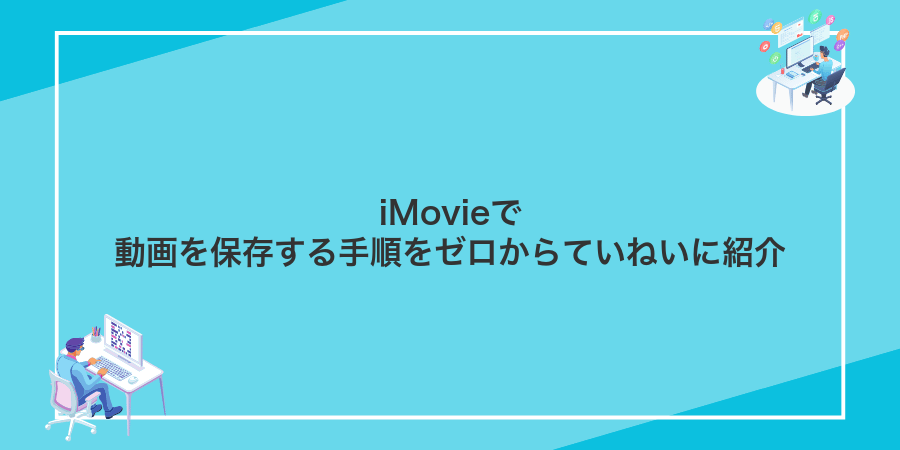
iMovieで編集した動画をきれいに保存するには、以下のポイントを押さえておくと安心です。
- 書き出し設定の選択:解像度やフレームレートを最適化して保存
- ファイル形式の決定:互換性の高いMP4(H.264)がおすすめ
- 保存先の管理:外付けドライブやクラウドに整理しておく
- 共有オプションの活用:YouTubeやSNSへ直接アップロード
プログラマー目線でひとつアドバイスをすると、可変ビットレートを使うと動画の容量を抑えつつ画質をキープできますよ。
これらの流れをつかんだら、次からは具体的な手順をゼロから丁寧に紹介していきますね。
メニューバーから書き出す方法
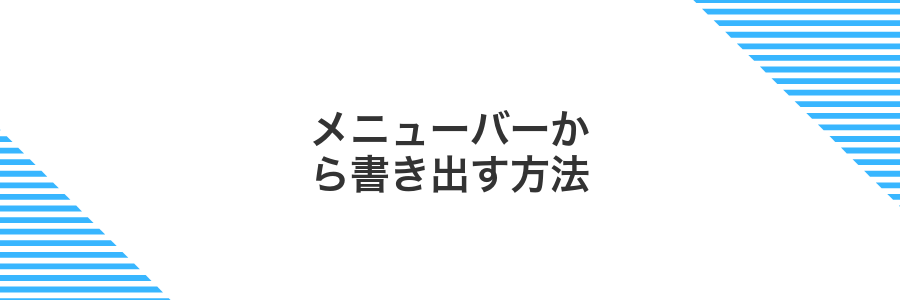
iMovieを編集し終えたら、画面上部のメニューバーから書き出せます。まず「共有」→「ファイル」をクリックすると、解像度や画質、圧縮方式をサッと選べる画面が現れます。余計な手間なくパッと出力できるから、編集結果をすぐ確かめたいときに便利です。
エンジニアのコツとして、よく使う設定はプリセットにしておくと再利用がラクになります。たとえばSNS向けの1080pや高画質の4Kなどを登録すれば、毎回同じ品質でワンクリック書き出しができます。
①プロジェクトを開く
iMovieを起動してウインドウ上部の「プロジェクト」を選択します。
表示されたプロジェクトブラウザで、開きたいプロジェクトのサムネイルをダブルクリックすると編集画面が立ち上がります。
②メニューバーのファイルをクリック
画面上部のメニューバーにカーソルを動かし、「ファイル」をクリックします。
なお書き出し操作をすばやく呼び出せる⌘+Eを覚えておくと、次回からもっとスムーズに進められます。
③共有を選んでファイルを書き出しを選択
動画を実際に書き出す準備ができたら、まず画面右上の共有アイコンをクリックしてメニューを開きます。ここからさまざまな出力先が選べるようになります。
共有メニューからファイルを書き出しをクリックします。アイコンがツールバーに見当たらないときは「…」を選ぶと表示されます。
出力形式や解像度はあとから変更できない場合があるので、書き出す前にしっかり確認しましょう。
④解像度と品質を好みに合わせて設定する
共有メニューの「ファイル」を選ぶと表示される設定画面で、「解像度」「品質」「圧縮方式」を調整できます。解像度は480p/720p/1080p/4Kから選べるので、用途に合わせて選択しましょう。
品質は「低」「中」「高」「ベスト(ProRes)」の順で上げられます。はじめは「高」あたりで試して、再生やファイルサイズに問題なければ「ベスト」にすると鮮明な仕上がりになります。
推奨の組み合わせは、SNS用なら720p+中、プレゼン用なら1080p+高、長期保存なら4K+ベストです。画面下部に表示される予想サイズを見ながら微調整しましょう。
高画質設定ほど書き出し時間とファイル容量が増えることに気をつけてください。
⑤保存先を選び保存をクリックする
保存先を指定する画面が開いたら、まず保存したいフォルダをクリックして選びます。よく使う「ムービー」フォルダやデスクトップは見つけやすいので便利です。
フォルダを選んだら、右下の「保存」ボタンをクリックしましょう。これで書き出しが始まります。終了までの時間は動画の長さや画質設定によって変わるので、気長に待ってくださいね。
外付けドライブに保存するときは、ドライブが「Mac OS拡張(ジャーナリング)」形式になっているか確認するとスムーズに書き出せます。
⑥進捗バーが消えたら書き出し完了
書き出しの進行状況はiMovieウインドウ上部に表示される進捗バーで確認できます。バーがゆっくり左から右へ伸び、最後に消えたら書き出しは完了です。
進捗バーが消えた直後はファイルの最終書き込みを行っている場合があるので、しばらく待ってからファイルを開いてください。
共有ボタンから書き出す方法
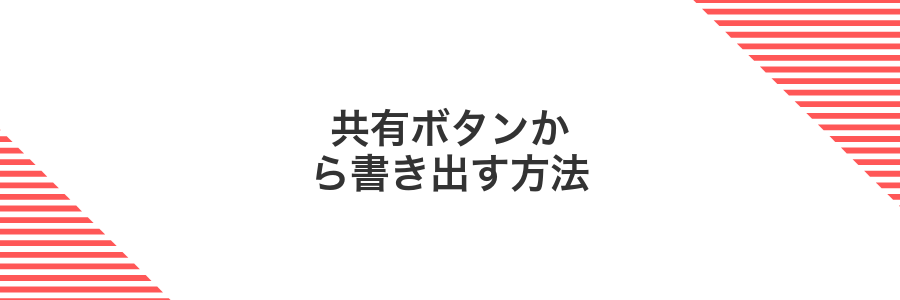
iMovieの画面右上にある共有ボタンを使うと、複雑な設定を見ずにサッと動画を書き出せます。初めてでも迷わず操作できて、書き出しの設定がまとめて用意されているのがうれしいポイントです。
- 手軽な操作:共有ボタンをクリックして書き出し先を選ぶだけでOK
- 複数プリセット:720pや1080pなど解像度の候補があらかじめ用意されている
- 直接アップロード:YouTubeやFacebookへワンタップで送信できる
- プレビュー確認:最終的な動画サイズや画質を共有前にチェックできる
①画面右上の共有ボタンをクリック
編集が終わったらウィンドウ右上にある□から矢印が飛び出すアイコンを探しましょう。マウスを合わせると「共有」と表示されるので、ここをクリックしてください。
注意点がある場合はここに記載:ウィンドウが小さいと共有アイコンが隠れやすいです。見当たらないときは画面を広げて再度探してみてください。
②表示されたメニューでファイルを書き出しを選ぶ
共有ボタンをクリックすると書き出し用のメニューがずらりと並びます。その中からファイルを選ぶと、解像度や圧縮の詳細設定画面が表示されます。
③タイトルやタグを入力し次へをクリック
書き出しウィンドウが表示されたら「タイトル」欄に動画名を入力します。次に「タグ」欄に関連ワードをカンマで区切って登録してください。
タグは小文字でまとめると検索にヒットしやすくなりますので試してみてください。
入力が済んだら右下の次へをクリックします。
④保存場所を決めて保存をクリック
書き出しダイアログの「場所」をクリックして、保存したいフォルダを選びます。
デスクトップやムービー(Movies)フォルダ、または任意のフォルダを選択してください。
保存先が決まったら、右下の「保存」ボタンをクリックして完了です。
日本語や空白を含むフォルダ名だと書き出しでエラーが出ることがあるので注意してください。
⑤書き出し状況を確認し終了を待つ
書き出しを始めると画面右上に進捗バーが表示されます。パーセンテージや残り時間を見ながら、完了するまで静かに待ちましょう。この間はiMovieを閉じたりMacをスリープさせたりしないようにしてください。
高解像度や長時間の動画ほど時間がかかるので、焦らず待つのがコツです。もし途中でやり直したくなったら、進捗バーの横にある中止ボタンをクリックすれば書き出しがキャンセルできます。
書き出しが終わったらFinderで出力先フォルダを開き、映像と音声に問題がないかしっかり確認しておくと安心です。
プロジェクトをこまめにバックアップする方法
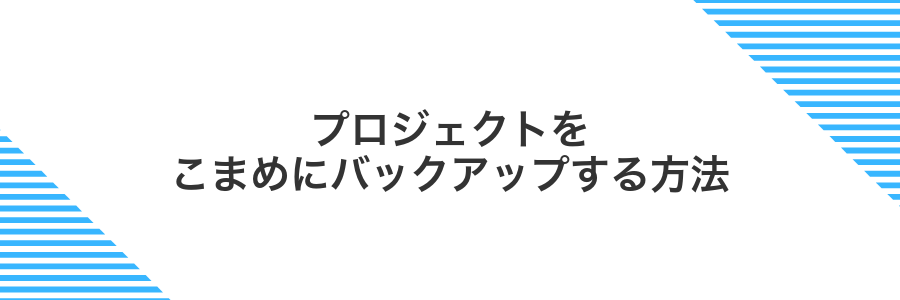
動画編集は編集中に思わぬエラーや操作ミスでプロジェクトが壊れることがあるため、こまめなバックアップが安心感につながります。
Time Machineを有効にしておけば、Mac内部の変更を自動で丸ごと記録してくれるので、万一のときは過去の状態にサッと戻せます。ただし容量を食いやすいので、バックアップ先のディスクは余裕をもって用意しましょう。
外付けSSDに編集フォルダだけをコピーする方法も有効です。編集中にFinderでドラッグ&ドロップするだけでいいので手軽ですし、Automatorでバックアップ用ワークフローを組んでおけば、ワンクリックで最新のプロジェクトが丸ごと保存できます。
特に長尺の動画や差し替えが多い案件では、編集中にファイル名を付けて複数世代を残しておくと、あとでどのバージョンでも呼び出せて便利です。
①iMovieを終了してFinderを開く
編集内容を保存する前にiMovieをきちんと閉じるとファイルの破損を防げます。まずはiMovieを終了してFinderを開きましょう。
画面左上の「iMovie」メニューから「終了」を選ぶか、⌘+Qで素早くアプリを閉じましょう。
DockにあるFinderアイコンをクリックしてウィンドウを出しましょう。保存先のフォルダにアクセスしやすくなります。
iMovieがバックグラウンドで動いたままだとプロジェクトファイルがロックされることがあります。
②ムービーフォルダのiMovieライブラリを探す
Finderを開いて、サイドバーのムービーをクリックします。
フォルダ内にあるiMovie ライブラリ.imovielibraryを探しましょう。ここにプロジェクトやイベントがまとまっています。
もし見つからない場合は、検索バーに「imovielibrary」と入力して絞り込んでみてください。
拡張子が見えにくいときは、Finderのメニューから表示→パスバーを表示をオンにすると、ファイルの場所がわかりやすくなります。
③ライブラリを外付けドライブへドラッグする
Finderでライブラリファイルが入ったムービーフォルダを開きます。
別ウィンドウで外付けドライブを表示し、iMovieライブラリ.imovielibraryをドラッグ&ドロップしてコピーします。
コピー中は進行バーが表示されるので完了までそのまま待ちましょう。
コピーが終わったら外付けドライブをFinder上で選び、「取り出し」をクリックして安全に取り外します。
外付けドライブの転送速度が遅いとコピーに時間がかかるので、余裕をもって作業してください。
④コピー完了後に日付を追記して管理する
Finderで書き出したファイルをコピーしたら、ファイル名をクリックして編集モードにします。
先頭にYYYY-MM-DD_形式で日付を入力すると、いつ作成したファイルか一目でわかります。
入力後にReturnキーを押すと名前が確定します。
保存後の動画をもっと楽しむアイデアを試そう
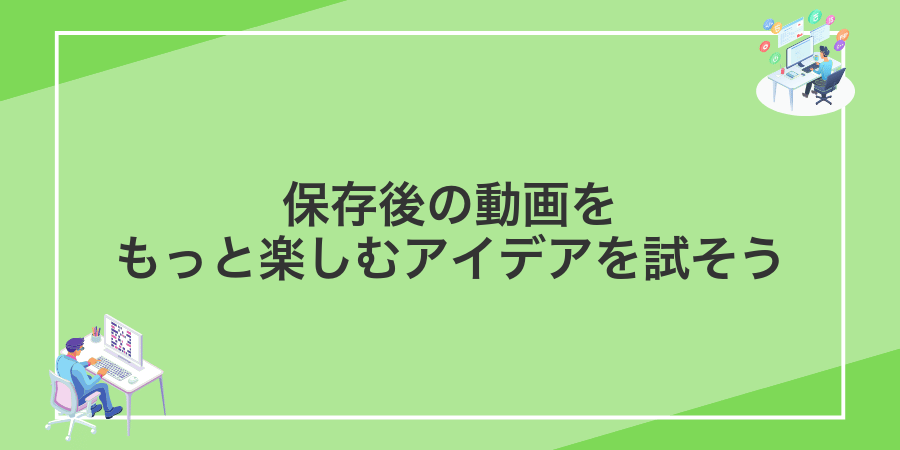
保存した動画をいろいろ楽しむアイデアを集めました。シーンや気分に合わせてお試しください。
| アイデア | こんな時に役立つ |
|---|---|
| SNSでシェア | 友達やフォロワーと感動の瞬間を共有したいときにぴったりです。 |
| スマートテレビで大画面鑑賞 | 家族や仲間と一緒に迫力ある映像を楽しみたいときにおすすめです。 |
| オリジナルDVDを作成 | 思い出を手元に残してプレゼントしたいときに便利です。 |
| サムネイルアートを作る | 動画を一覧で見やすく整理したいときやブログに載せるときに役立ちます。 |
| 短いGIFに変換 | メールやチャットで手軽に面白いシーンを送信したいときに活躍します。 |
この一覧をヒントに、お気に入りのシーンをより身近に感じながら楽しんでみてください。
メール添付に最適なサイズへ再圧縮する
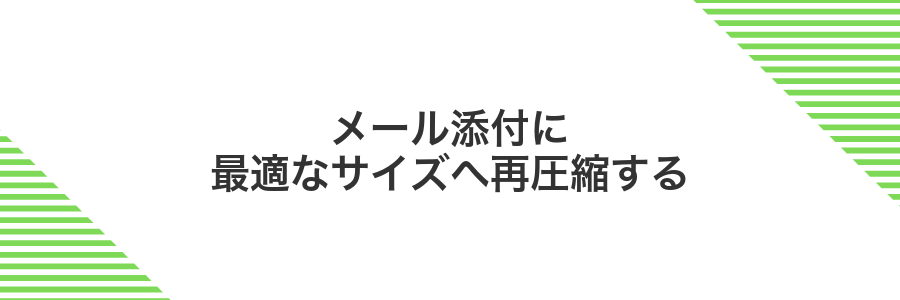
メールに添付しやすいサイズにしたいときは、iMovieから書き出した動画をもう一度軽く圧縮しておくのがおすすめです。特に20MB前後に抑えると、送信エラーや受信者のダウンロード負荷が減ります。Macに最初から入っているQuickTime Playerや、ffmpegのような無料ツールを使えば、難しい操作なしでサクッと再圧縮できます。
- QuickTime Playerで“書き出し>ファイルサイズを小さく”を選ぶだけ
- ffmpegならコマンド一行でビットレート指定が自在
- 無料ツールを組み合わせれば、動きの少ない動画ほど軽くできる
QuickTimeでファイルを開きサイズをカスタム設定
Finderで書き出したムービーを見つけたら、右クリックから「このアプリケーションで開く」→QuickTime Playerを選びます。見慣れた画面でサクッと確認できます。
上部メニューの「書き出す」→「書き出す…」をクリックします。ダイアログの「解像度」を「カスタム」に切り替え、必要な横幅と高さをピクセルで入力してください。入力後は「保存」を選べば完了です。
元の動画より大きいサイズを入力すると画質が粗くなるので、オリジナル解像度を超えないように設定してください。
圧縮後にメールアプリへドラッグして送信
圧縮が終わったら、Finderからメールアプリにパッとドラッグしてみましょう。新規メッセージに添付されるので、とってもかんたんです。
Finderで.zipファイルを選択したまま、Dockのメールアイコンへスライドします。新規ウインドウが自動で開き、添付完了のチェックマークが表示されるので確認してください。
メールの添付は25MBまでが目安です。それ以上のサイズだと送信できないので、Mail Dropを活用するかクラウドリンクを併用しましょう。
AirDropでiPhoneへ即共有する

AirDropを活用すると、Wi-FiとBluetoothがオンの近くにあるiPhoneへサクッと動画を転送できます。
ケーブル不要で高画質のまま送れるうえ、クラウドにアップロードする手間も不要です。動画サイズが大きくてもストレスなくやりとりできるのがうれしいポイントです。
転送先のiPhoneは画面ロック解除しておく必要がありますが、その一手間だけ守れば、手軽に友だちや自分のスマホで再生できるようになります。
Finderで動画を右クリックし共有からAirDropを選択
Finderで保存した動画ファイルをAirDropで送るときは、まずファイルを表示して右クリックでメニューを開きます。
Finderで目的の動画を見つけたら、ファイル上で二本指タップまたはcontrolキーを押しながらクリックしてメニューを表示します。
メニューから共有をポイントし、サブメニューに出るAirDropをクリックします。
AirDropは受信側のMacやiPhoneが近くにあって、受信設定が「すべての人」もしくは「連絡先のみ」になっている必要があります。
受信先のiPhoneをタップして転送する
AirDrop画面に相手のiPhone名が表示されたら、その名前をしっかりタップします。
タップ後、iMovieから送信が始まり、受信側のiPhoneに「受け入れる」ボタンが表示されます。
受け入れをタップすれば動画の転送が完了し、自動的に〈写真〉アプリに保存されます。
受信側のiPhoneがスリープ中だと表示されないことがあるので、画面をオンにしておいてもらいましょう。
macOS標準の写真アプリへ取り込んで整理する
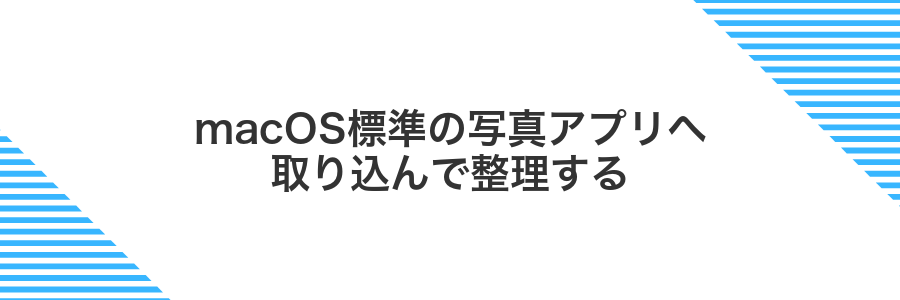
動画をiMovieから書き出したあと、そのまま写真アプリに取り込むと整理がスムーズになります。写真アプリなら写真と一緒に動画をまとめられるので、家族の思い出やイベント録画をまとめて眺められるのがうれしいポイントです。
アルバムやキーワードで分類できるので、撮影日やテーマごとにまとめておけばササッと探し出せます。iCloud写真をオンにしておけば、iPhoneやiPadとも自動で連携されるので、どこからでも動画を楽しめます。
写真アプリを開きメニューバーの読み込むを選択
まずDockやLaunchpadから写真アプリを起動してください。
画面上部のメニューバーにあるファイルをクリックするとメニューが表示されますので、その中から読み込むを選んでください。
- 写真アプリを開く:DockかLaunchpadからアプリアイコンをクリック。
- ファイルメニューを表示:画面上部のファイルをクリック。
- 読み込むを選択:表示された一覧の中から読み込むをクリック。
外部カメラやSDカードが接続されていないと「読み込む」が押せないので、先に接続を確認しましょう。
書き出した動画を選びアルバムを作成して保存
MacのDockやSpotlightからPhotosを開きます。写真と動画を一括管理できるので便利です。
メニューの「ファイル」→「読み込み」を選び、iMovieから書き出した動画ファイル(.movまたは.mp4)を選択して読み込みます。
読み込み後、サイドバーの「アルバム」→「+」ボタンで新しいアルバムを作ります。わかりやすい名前をつけると後から探しやすいです。
写真ライブラリからインポートした動画を選択し、右クリックで「アルバムに追加」を選んで先ほど作ったアルバムを指定します。
よくある質問
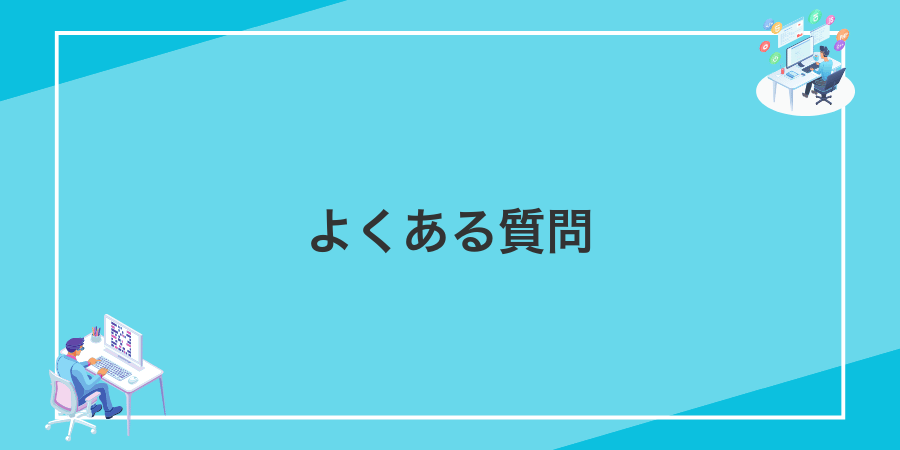
iMovieで書き出した動画はどこに保存されますか?
- iMovieで書き出した動画はどこに保存されますか?
-
デフォルトではMacの「ムービー」フォルダに保存されます。Finderでサイドバーの「ムービー」を選ぶと、iMovie Mediaフォルダがあり、その中の「Exports」に入っているはずです。プログラマー経験から言うと、保存先をカスタムしたいときは書き出し設定の直前画面で「場所を変更」をクリックすると、任意のフォルダにサクッと移動できます。
書き出しに時間がかかってしまいます。どうすれば速くなりますか?
- 書き出しに時間がかかってしまいます。どうすれば速くなりますか?
-
動画の解像度が高いほど処理負荷が上がります。まずは書き出し画面で解像度を720pに落としてみてください。実体験では、4Kから1080pに変えただけで半分以下の時間になりました。また、他のアプリを終了してCPU/GPUリソースを空けると、さらに短縮できます。
MP4以外の形式で書き出す方法はありますか?
- MP4以外の形式で書き出す方法はありますか?
-
標準の書き出しではMP4(.movコンテナ)が中心ですが、Apple Compressorを組み合わせると多彩なフォーマットに対応します。プログラマー目線でのコツは、まずiMovieから高品質のProResで書き出し、そのファイルをCompressorでH.264やHEVC、GIFなどに変換すると画質劣化を抑えつつ形式を自由に選べます。
書き出しボタンがグレーアウトしているのはなぜ?
書き出しボタンがグレーアウトしているのは、iMovieがまだ動画を出力できる状態にないサインです。
- タイムラインにメディアがないか選択されていない
- 編集中のプロジェクトがレンダリング待ちの状態
- 保存先のディスク容量が不足している
- 使用しているクリップの形式がiMovie未対応
まずは編集画面でタイムライン上にクリップが配置されているか、そしてプロジェクト名がオレンジ色でアクティブになっているかを確認しましょう。
もしレンダリングマークが右上に出ていたら少し待つか、書き出し前に「ファイル」メニューから「レンダリング」を実行するとスムーズになります。
それでもボタンが活性化しない場合は、Finderで保存先の空き容量をチェックしたり、iMovieを再起動すると改善しやすいです。
4Kで保存できないの?
iMovieで4K動画を出力するには、使っているiMovieとmacOSのバージョン、そして素材の解像度が揃っていることが大切です。条件がそろわないと、書き出し画面でそもそも「4K(2160p)」の選択肢が表示されません。
- iMovieのバージョン:10.1以降で4K書き出しに対応。
- macOSのバージョン:Mojave以降を使うと安定して処理できます。
- クリップの解像度:元素材が4Kでないと高解像度で保存できません。
- 書き出し設定:共有→ファイル→解像度で「4K(2160p)」を選ぶ。
注意点:4K動画はデータサイズが大きくなるので、保存先の空き容量を事前に確認してください。
これらを整えてから書き出せば、高精細な4K動画を手軽に保存できます。
ファイルサイズをもっと小さくできる?
iMovieでは書き出し時に解像度やビットレートを調整できるから、パソコンのHDDやクラウドストレージに余裕がないときにも安心だよ。
具体的には、共有メニューから「ファイル」を選んで、解像度を「720p」や「540p」に下げたり、品質を「中」や「低」に設定したりするとぐっとファイルサイズがダウンするよ。動画の内容によっては画質の差が気にならないから、SNS投稿やメール添付にはピッタリだね。
また、プログラマー的なコツとして、まず小さなクリップでテスト書き出しをしてみると、最適なビットレートの目安がつかめるよ。いくつか試して容量と画質のバランスを見極めてみよう。
字幕を入れたまま書き出す方法は?
最新のmacOS Venturaで動作しているiMovieの標準機能を使うと、編集した字幕を動画へ直接埋め込んで書き出せます。外部サービスや煩雑な作業は要らないので初めてでも安心です。
やり方はシンプルです。画面右上の共有ボタンから「ファイルを書き出す」を選び、オプションの詳細設定でキャプションを埋め込むをチェックすればOKです。これだけで字幕入りの動画ファイルが生成されます。
この方法なら書き出し後に字幕ファイルを別途合成する必要がなく、どの再生環境でも同じ表示で楽しめます。YouTubeやSNSへのアップロードもスムーズになるのでおすすめです。
途中で停止した書き出しは再開できる?
大前提としてiMovieには途中で止めた書き出しをそのままピタッと再開する機能はないです。でも長時間の動画を書き出していると、ネットや電源の不安定さで書き出しが途中で止まることがありますよね。
そんなときにおすすめなのが、プロジェクトをチャプターやクリップ単位で分割しておく方法です。クリップごとに書き出しを行えば、途中で止まっても止まった箇所以降のクリップだけを改めて書き出せばOKです。実際に経験したところ、長尺イベント動画をこのやり方で処理すると、トラブルが減ってスムーズに完成できました。
まとめ
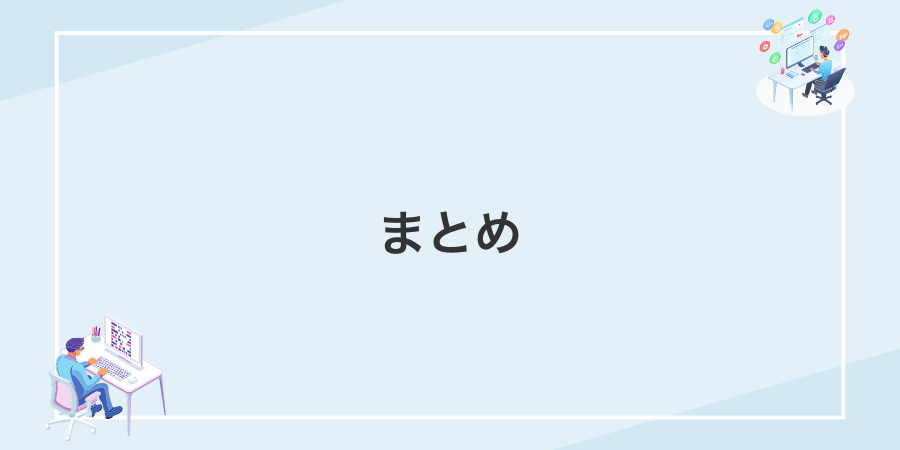
iMovieで作成した動画は、メニューバーから「共有」「ファイル」を順に選んで、解像度や品質を決めるだけでパソコンに保存できます。
この手順を覚えておけば、YouTubeやSNSへのアップロードもラクラクです。いろいろな書き出し設定を試して、自分好みの動画を楽しんでください。