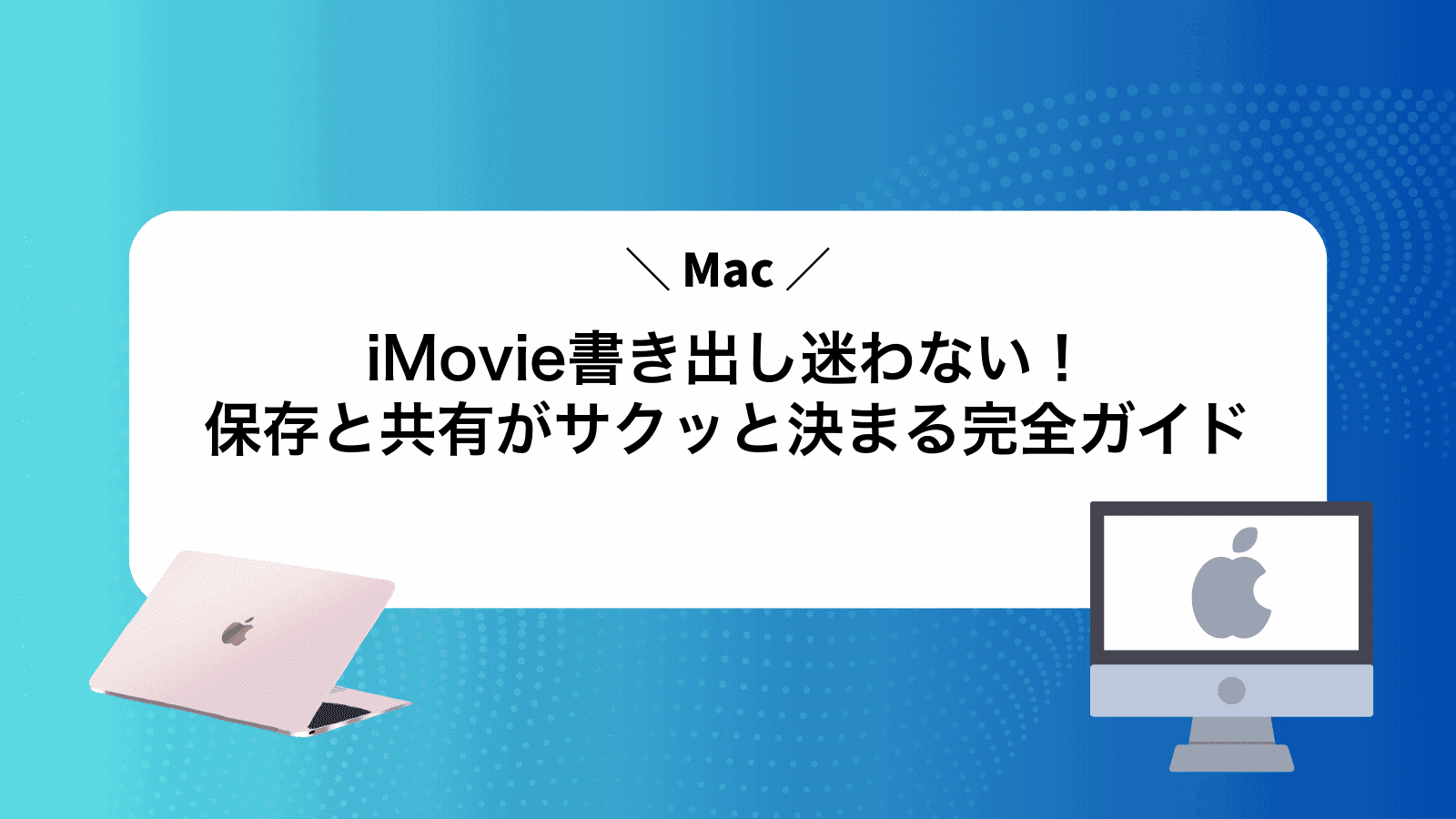iMovie で編集した動画をいざ書き出ししようとした瞬間、どの設定を選べば良いのか戸惑ってしまいますよね。
このページでは、解像度やファイル形式の違いをやさしく示しつつ、実際に保存ボタンを押すまでを画像付きで順番に案内しますので、初めてでも失敗なく完成ファイルを手にできます。
動画をスムーズに届けたい方は、まずはひと呼吸して準備を整え、以下のステップを一緒に進めてみてください。
iMovieで動画を書き出す基本ルート
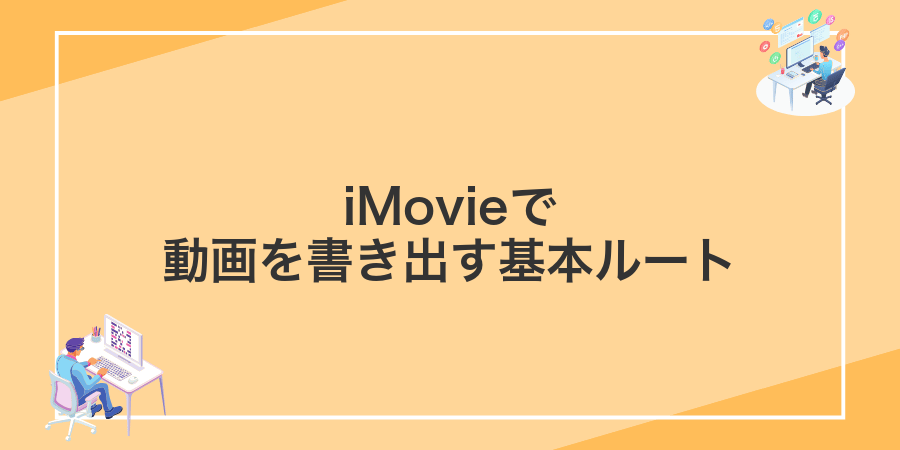
iMovieで編集した動画を完成させたあと、どの書き出し方法を選ぶかで「あれこれ迷っちゃう」という声をよく聞きます。
- ファイルとして保存:Macの任意フォルダに.movや.mp4で書き出しておくと、後から編集や共有先を自由に選べるので安心です。
- 直接アップロード:YouTubeやFacebookと連携して、そのままネット上に公開できます。ログイン情報を設定しておくとスムーズです。
- AirDropで受け渡し:近くにあるiPhoneやiPadにワイヤレスで送信できます。大容量ファイルでもケーブルいらずで助かります。
- メールやメッセージで共有:短いクリップなら直接添付して送るのが手軽。長い動画は容量に注意してください。
エンジニア視点だと、大きな動画は最初にローカルに保存してから別サービスにアップする流れがトラブルも少なくおすすめです。
ファイルに書き出してMacに保存
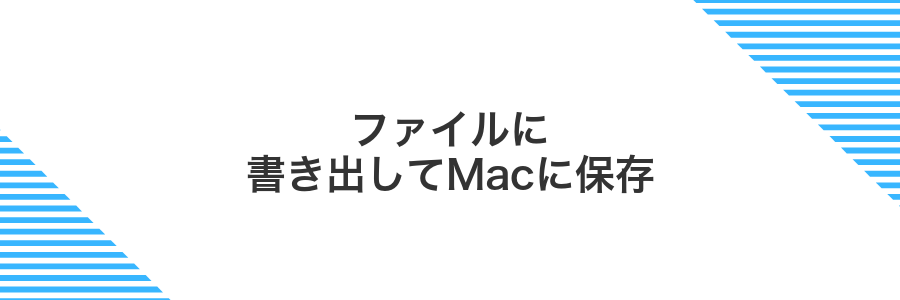
書き出した動画ファイルをそのままMacの好きな場所に保存できます。手元にデータが残るので、あとで手軽に再編集したりほかのアプリで開いたりしたいときにうれしい方法です。
- ファイル形式:MP4やMOVでほぼすべての環境で再生可能
- 保存場所:デスクトップや外付けドライブで整理しやすい
- 再読み込み:iMovieにドラッグ&ドロップでスムーズに取り込める
プログラマーらしいワンポイントとしては、書き出し設定で高品質(1080p)とH.264を選ぶと、画質キープしつつファイルサイズをおさえられます。
①プロジェクトを開き上部の共有ボタンをクリック
iMovieを起動して、書き出したいプロジェクトをダブルクリックで開きます。編集画面が表示されたら、ウィンドウ右上にある四角い共有アイコンを探してクリックしましょう。
②ファイルを選択して次へを押す
共有ウィンドウに表示されたムービーファイルをクリックすると選択できます。ここでファイル名や保存先を確認してください。
そのままで問題なければ右下の「次へ」ボタンを押します。Finderが開いて保存場所を指定できるようになります。
外付けドライブを選ぶときは書き込み速度と空き容量をチェックしないと途中で止まるかもしれません。
③解像度と品質をドロップダウンで決める
画面右上の共有アイコンをクリックして「ファイル」を選び、書き出しダイアログを呼び出します。
ダイアログ内の「解像度」ドロップダウンから希望の出力サイズを選択します。高画質を優先するなら1080p、ファイルサイズ重視なら720pがおすすめです。
続けて「品質」ドロップダウンを開き、「高品質」「中品質」「低品質」から用途に合わせて選びます。ウェブ配信なら中品質でも十分きれいに見えます。
高解像度+高品質はファイルサイズが大きくなります。外部ストレージの空き容量を確認してから書き出しましょう。
④保存場所を選んで書き出しを開始
書き出しダイアログが表示されたら、左側のサイドバーから動画を保存したいフォルダを選びます。
ファイル名を変更したいときは、画面上部のファイル名欄をクリックしてわかりやすい名前に書き換えましょう。
保存先とファイル名が決まったら、画面右下にある「保存」ボタンをクリックすると書き出しが始まります。
保存先のディスクに十分な空き容量がない場合、書き出し中にエラーになるので注意してください。
⑤進行状況を確認し完了通知を待つ
書き出しが始まると共有ダイアログに進行状況バーと百分率が表示されます。
動画の長さや設定によってかかる時間が変わるので、ここで進み具合をチェックしましょう。
書き出し中はCPU使用率が上がるので、大きなアプリを同時に動かさないとサクサク進みます。
ダイアログを閉じるとバーが消えるため、完了まで閉じずにそのまま待ちましょう。
YouTubeに直接アップロード
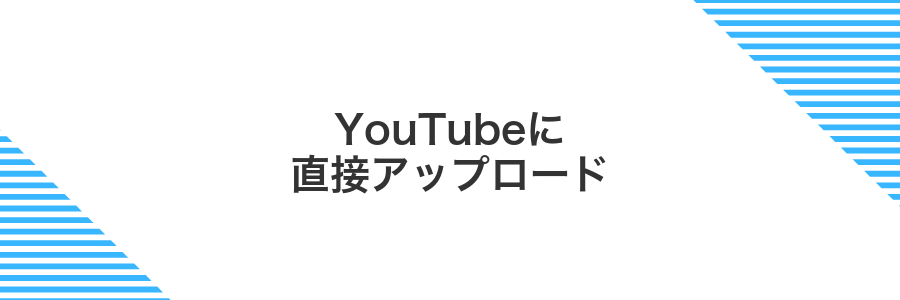
iMovieから書き出しと同時にYouTubeへ動画をアップロードすると、ムダな手間が省けてとってもスムーズです。
プロジェクトを完成させたら共有メニューから「YouTube」を選ぶだけで、タイトルや説明文の入力画面がそのまま現れます。解像度や公開設定もiMovie内でパパッと整えられるので、ファイル書き出し→アップロードという流れを一度に済ませたいときにぴったりです。
①共有ボタンからYouTubeを選ぶ
iMovieの右上にある四角に上向き矢印のアイコンをクリックします。出てきたメニューの中からYouTubeを選んでください。読み込みに少し時間がかかることがありますが、そのまま待って進めましょう。
YouTubeがメニューに表示されない場合は、システム環境設定の「インターネットアカウント」でYouTube連携状況を確認してください。
②Googleアカウントでサインイン
共有先を選んだあと表示されるサインインウィンドウで、使いたいGoogleメールアドレスを入力して「次へ」をクリックします。
続いてパスワードを入れて「ログイン」を押すと、二段階認証の画面に進むことがあります。届いた認証コードを入力すれば準備完了です。
ブラウザがバックグラウンドで開いても大丈夫です。iMovieに戻ると自動で認証情報が反映されます。
③タイトルと説明を入力し公開範囲を選ぶ
書き出しウインドウでまずは動画のタイトルと説明を入力し、誰に公開するかを選びます。
「タイトル」の欄に動画の内容がひと目で分かるキーワードを入れます。「説明」欄には見どころや関連リンクを簡潔にまとめるとあとで探しやすくなります。
プライベート、限定公開、または全員公開から適切な公開範囲をチェックします。社内共有なら限定公開、公開向けなら全員公開を選んでください。
説明欄に個人情報や社外秘リンクを入れないように注意してください。
④アップロードをクリックして完了を待つ
共有先を選んだら「アップロード」をクリックします。ここからは自動で進むのでそのまま見守りましょう。
プログレスバーが最後まで進むと完了です。途中でスリープに入らないよう、スリープ設定をオフにしておくとスムーズですよ。
アップロードが終わったらブラウザで公開先を開いて、動画がちゃんと表示されているかチェックしましょう。
AirDropでiPhoneに転送

AirDropを使うとiMovieで完成したムービーをMacからiPhoneへすぐに送れます。近くにあるAppleデバイス同士でWi-FiとBluetoothを活用してケーブルなしでサクッと転送できるのが楽ちんです。
- ケーブル不要だからデスク周りがすっきり
- 転送スピードが速い大きな動画でもストレスフリー
- 追加アプリ不要標準機能だけで使い始められる
こんな人におすすめです。ケーブルを探す手間を省きたい方や、外出先ですぐに動画をiPhoneでチェックしたい方にはぴったりの方法です。
①共有ボタンでAirDropを選ぶ
動画のプレビュー画面右上にある共有アイコンをタップします。するとiOSやmacOSの最新バージョンで整えられた共有シートが開きます。
一覧からAirDropを選ぶと、近くのAppleデバイスを自動で検出します。
送り先のデバイスアイコンをタップすると、承認を待ってファイル送信がスタートします。
②書き出し設定を確認して次へ
共有メニューから「ファイル」を選ぶと書き出し画面が表示されます。ここで解像度(720p/1080p/4K)、品質(低/中/高/最高)、圧縮方法(高速/品質優先)を確認しましょう。
SNS向けなら1080p高画質、Web向けなら720p中画質+高速圧縮が使いやすいです。用途に合った設定を選んで「次へ」を押してください。
③受け取り側iPhoneを選択
共有シートに表示されたAirDropの一覧から、送信先のiPhoneを探してクリックしてください。「〇〇のiPhone」のような名前で出てきます。
選んだら自動で転送が始まり、iPhone側で受け取りのダイアログが出るので「受け入れる」をタップしてください。
iPhoneがスリープ中だと検出されないことがあります。ロック解除しておくとスムーズです。
④転送が終わったら写真アプリで再生を確認
SpotlightやDockから写真アプリを開きます。
サイドバーのライブラリで最近の項目を選び、転送したメディアを見つけてください。
目的の動画サムネイルをダブルクリックするとプレビュー画面が立ち上がります。再生ボタンを押して映像と音声に問題がないかチェックしましょう。
動きが引っかかる場合は一度ウインドウを閉じ、SpotlightからQuickTime Playerを開いて再度再生してみると解像度やエンコードの違いによる不具合を回避できます。
書き出し機能をもっと楽しむ応用ワザ
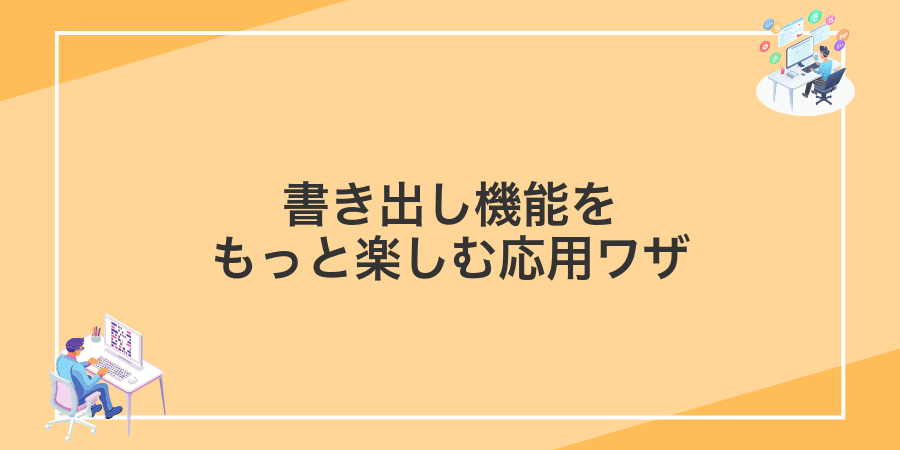
書き出し機能を使いこなすと、動画制作がもっと楽しくなります。ここでは試してほしい応用ワザをまとめたので、シーンに合わせてピックアップしてみてください。
| 応用ワザ | 使いどころ・役立ちポイント |
|---|---|
| カスタムプリセット設定 | 解像度や圧縮レートを保存して、何度も同じ設定でサクッと書き出せる |
| HEVC形式で圧縮 | 高画質のままファイルサイズを抑えたいときに便利 |
| ワークフローの自動化(Automator連携) | 書き出し後に指定フォルダへ自動で移動&リネームできるから手間いらず |
| サムネイル画像の一括抽出 | プレビュー用やSNS投稿用にキーフレームが手軽に手に入る |
| 直接SNSへ投稿 | 書き出しと同時にシェアシート起動でワンタップ投稿が叶う |
字幕付きのSNS短縮版を作ってシェア
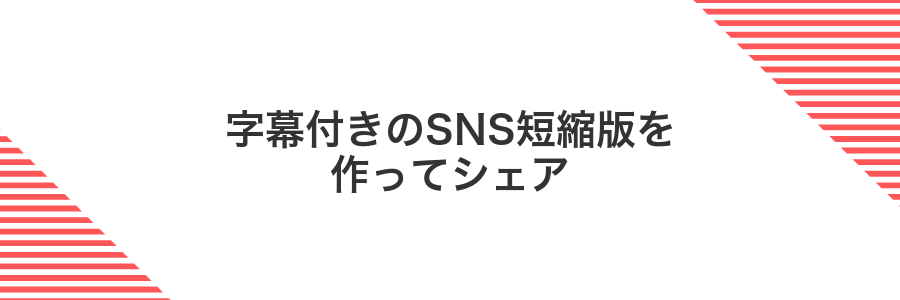
SNSでは音声オフで再生されることが多いため、字幕付きの15~60秒程度の短い動画にまとめると、より多くの人に最後まで見てもらいやすくなります。
iMovieなら元の長い動画から不要な部分をサクッとカットして、テキストツールで字幕を流し込むだけでOKです。編集画面に慣れていない人でも直感的に操作できるので、初めてでも迷いません。
- 音声なしでも内容が伝わるからミュート再生でも効果的
- 短くまとめることでSNSの規定時間にぴったり収まる
- スマホ画面でも読みやすい字幕サイズと配色にできる
こうしたメリットから、iMovieでサクッと作れる字幕付きショート版は、InstagramリールやTikTok、YouTubeショートなど、さまざまなSNSで活用しやすいスタイルです。
タイムラインで範囲を選んでクリップを分割
ツールバーの「範囲選択ツール」アイコンをクリックするか、Rキーを押します。タイムライン上のクリップをドラッグして、分割したい部分を選んでください。
選択した範囲を右クリックして「クリップを分割」を選びます。キーボードショートカットなら⌘Bでも実行できます。
タイトルメニューから字幕テンプレートを挿入
iMovieの上部にあるタイトルをクリックして、用意された字幕テンプレート一覧を表示します。
好きな字幕スタイルを選んで、タイムライン上の表示させたい位置にドラッグ&ドロップします。再生ヘッドの位置に合わせると便利です。
プレビュー画面上のテキストをダブルクリックして、内容やフォントサイズを入力・調整しましょう。
再生ヘッドの位置が字幕の開始位置になるため、配置前に確認してください。
共有ボタンでファイルを選び1080pに設定
画面右上の共有アイコンを押します。飛び出すメニューで「ファイル」を選ぶと書き出し設定画面が開きます。
設定画面で「解像度」をクリックし、1080pを選んでください。必要に応じて品質や圧縮方法も調整できます。
完成動画をInstagramにドラッグして投稿
SafariやChromeでinstagram.comにアクセスし、ログイン後に「+」アイコンをクリックして投稿画面を表示します。
Finderで書き出した動画を選んで、そのままブラウザのアップロード枠にドラッグします。プレビューが表示されたら正しく読み込まれています。
アップロードできる動画はMP4形式かつ60秒以内です。長い動画は自動でカットされるかエラーになるので要注意。
連番静止画を書き出してGIFアニメを作成

動画を1フレームずつ連番の静止画として出力してから、それらの画像をGIFアニメにまとめる方法があります。こうすると、好きな範囲だけを抜き出してループを作ったり、画質を保ったまま短い動きを簡単に共有したりできます。
動きの確認やSNS向けのループGIFをサクッと作りたいときにぴったりです。実践者ならではのコツとして、ImageMagickなどのツールを使うと、一括処理で画像を連結したりループを調整したりがスムーズに進みます。
書き出しメニューでフレームを保存を選ぶ
動画の好きなシーンをそのまま画像として取り出せる便利な方法です。保存したいフレームをピタリと決めたら、さくっと静止画にしてしまいましょう。
タイムラインの再生ヘッドをドラッグして、ぴたりと目的のシーンが表示される位置で止めます。
画面右上の共有アイコンをクリックし、表示されたリストからフレームを保存を選びます。
ダイアログが表示されたら、保存したい名前とフォルダを設定し、保存をクリックします。
プレビューでコマを確認し保存
タイムライン上の再生ヘッドを動かして、気になるコマをチェックします。特にトランジションやテキスト表示のタイミングがずれていないかしっかり確認しましょう。
一度動画を通常速度で再生したあと、停止したい箇所でスペースキーを押し、左右矢印キーでフレーム単位の動きを見て微調整すると見落としを減らせます。
画面右上の共有ボタンをクリックし、「ファイル」を選びます。解像度や品質、保存先を自分の用途に合わせて設定してください。
「次へ」を押して保存先を指定し、「保存」をクリックしたら書き出しスタートです。完了後はFinderで開いて、念のためもう一度再生してチェックしておくと安心です。
プレビューアプリで画像を選び書き出しをGIF指定
FinderでGIFにしたい画像を⌘キーを押しながら複数選択し、右クリックメニューから「このアプリケーションで開く>プレビュー」を選びます。
プレビュー左側のサムネイル一覧をクリックし、⌘+Aで読み込んだ画像をすべて選択します。
上部メニューの「ファイル>書き出す」をクリックします。もしくは⌘+Shift+Sを押しても呼び出せます。
フォーマットのプルダウンから「GIF」を選び、保存先を決めて「保存」をクリックします。
GIFは256色までしか扱えないため、カラーパレットが多い画像は色味が変化することがあります。
Automatorで複数プロジェクトを一気に書き出す

iMovieプロジェクトがたくさんあると、一つずつ書き出す作業が地味に疲れますよね。Automatorを使うと、あらかじめ作った“書き出しワークフロー”にプロジェクトをまとめて放り込むだけで、一気に処理が進んでくれます。
いちどワークフローを組んでしまえば、次からはドラッグ&ドロップで実行するだけ。書き出し設定を何度も入力しなくていいから、時間をぐっと節約できます。ファイル名に日付を自動で付けたり、エラー時に通知したりと、プログラマーらしいカスタマイズも楽しめるのが魅力です。
Automatorでワークフローを新規作成
Automatorを使った自動化を始めるには、まず新しいワークフローを作成しましょう。ここではMac標準のAutomatorアプリを立ち上げて、ワークフロー書類をゼロから用意する具体的な手順を紹介します。
Spotlight(⌘+スペースキー)で「Automator」と入力して起動するか、Finderの「アプリケーション」フォルダからAutomatorをダブルクリックしてください。
起動後に表示される書類タイプ選択画面で「ワークフロー」をクリックし、「選択」を押します。
メニューバーから「ファイル」→「保存」を選び、分かりやすい名前を付けて保存フォルダを指定します。後から見つけやすいように、プロジェクトごとにサブフォルダを作ると便利です。
Automatorを初めて使う場合、最初の起動時に「システム環境設定」での権限確認が出ることがあります。そのときは「許可」を選んで続けてください。
iMovieスクリプトアクションを追加
iMovieの共有メニューに自分専用のスクリプトアクションを登録すると、毎回同じ書き出し設定をワンクリックで呼び出せます。
SpotlightやLaunchpadからAutomatorを開き、「クイックアクション」を選択します。
画面上部の「ワークフローが受け取る現在の項目」を「ムービーファイル」に設定します。
左側の検索バーに「iMovie」と入力して、利用可能なアクションを表示させます。
検索結果から「ムービーを書き出す」をドラッグして、右側のエリアに配置します。
解像度やフォーマット、保存先を自動で指定するように各項目を設定します。
名前を付けて保存(例:iMovieエクスポート)し、Automatorを閉じます。
保存後はiMovieを再起動すると、共有メニューに追加したアクションが表示されやすくなります。
保存して実行し連続書き出しを待つ
ファイル名や保存先を最終確認したら保存をクリックします。
書き出しが始まるとiMovie上部に進捗バーが現れ、残り時間や進行状況が表示されます。プロジェクトを続けて書き出す場合は同じ手順をくり返すと、iMovieが自動で順番に処理してくれます。
書き出し中はMacがスリープしないよう、システム環境設定の「省エネルギー」をチェックしておきます。
よくある質問
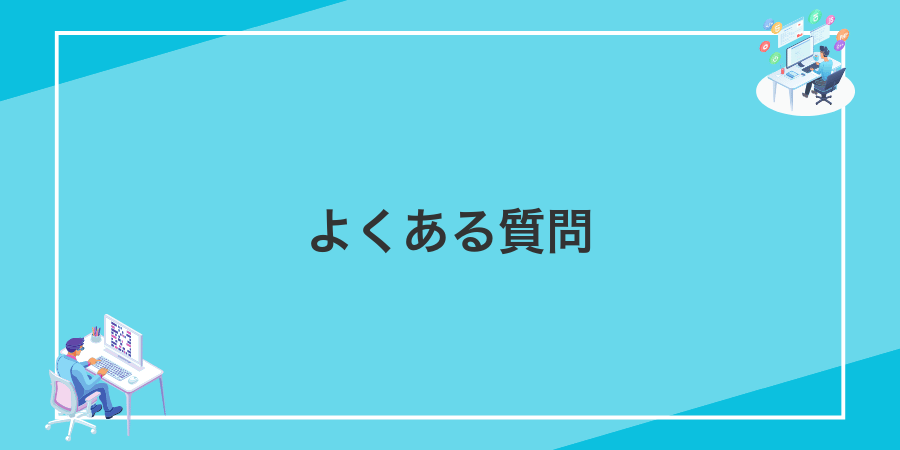
書き出しがなかなか進まないのはなぜ?
- 書き出しがなかなか進まないのはなぜ?
動画の長さや解像度が高いと処理に時間がかかります。特にSSDの空き容量が少ないと一時ファイルの読み書きで遅くなることが多いです。ほかの重いアプリを閉じてみてください。
書き出した動画が再生できず真っ黒になる
- 書き出した動画が再生できず真っ黒になる
コーデックに問題があることが多いです。デフォルトの「1080p HD」プリセットなら汎用性が高いのでお試しください。それでも再生できない場合はQuickTime Playerで開いてみると原因がわかることがあります。
ファイルサイズを小さくしたいときは?
- ファイルサイズを小さくしたいときは?
書き出し設定で解像度を720pに落としたり、ビットレートを下げるとサイズをかなり抑えられます。プログラマー視点では一度低品質版を作成してテスト再生し、見た目を確認すると安心です。
YouTubeに直接アップロードできないときは?
- YouTubeに直接アップロードできないときは?
「共有」>「YouTube」を選ぶ前に、システム環境設定の「インターネットアカウント」でGoogleアカウントを追加しておくとスムーズです。接続済みかどうかを確認してから試してみてください。
書き出しが途中で止まるのはなぜ?
書き出しが途中で止まってしまう原因はいくつかあります。プロジェクトが重くなってメモリが追いつかない、保存先のディスクに空き容量が不足している、Macがスリープして処理が中断される、取り込んだ動画や音声の形式がiMovieと相性がよくない、などです。
対策としては、不要なアプリを閉じてメモリを空ける、ディスクの使用状況をチェックしてしっかり空きを確保する、システム環境設定からスリープをオフにしておく、もし相性が不安な素材があれば一度QuickTime Playerなどで別形式に書き出してから読み込む、といった方法を試してみてください。
最適な解像度と品質はどれを選べばいい?
iMovieで動画を書き出すとき、画面に並ぶ解像度と品質の項目に目移りしちゃいますよね。普段使いやお披露目したい場面に合わせて、どれを選べばいいかをサクッとまとめました。
- 720p:SNSで手軽にシェアするならスマホで撮った日常映像や短いクリップをSNSにアップしたいときにぴったり。ファイルサイズが小さめなので、アップロードもスムーズです。
- 1080p:YouTubeや家族のアルバム向きほどよい高画質で、ほとんどの画面で美しく再生できます。プログラミングの解説動画や旅行記など、ちょっと大きめのスクリーンでも見栄えします。
- 4K:テレビやプロジェクターで映える細かいディテールがくっきり残るので、完成度の高い作品を公開したいときにおすすめ。容量は大きくなるので、クラウドや外付けドライブへの保存が安心です。
品質は「高」「中」「低」から選べますが、こだわりがなければ「高」のままにしておけばOKです。容量と画質のバランスを自分で調整したいときは「カスタム」を開いてビットレートを設定してみると、プログラマー視点のこだわり派にも楽しめます。
音ズレが起きたときの直し方は?
動画の音と映像がずれるときは、Timeline上で音声を分離して動かせるiMovieの機能を使うのがおすすめです。
まずはクリップをダブルクリックして「オーディオを分離」を選んでみてください。そのあと手動で音声トラックを左右にスライドさせると、映像にぴったり合わせやすくなります。
ほかにもプロジェクトのフレームレートを素材と同じにそろえてから読み込むと、大きなズレが起きにくくなるので、撮影時と同じ設定で作業するのもプログラマーっぽいコツですよ。
容量が大きすぎるときの対処法は?
動画データを書き出したらファイルサイズが巨大になって「あれどうしよう」と頭をかしげたことありませんか?そんなときはほんの少し設定を変えるだけでグッと軽くなります。
容量を減らす方法は大きく3つあります。それぞれの特徴をつかめばサクッと選べますよ。
- 画質と解像度の調整:720pや1080pに落とすだけで容量が半分以下になることもあります。
- 不要シーンのトリミング:撮影開始前や終了後の余白をカットするだけで軽量化できます。
- 外部ツールでの再圧縮:HandBrakeなどでビットレートを細かく指定しながら圧縮すると効率的です。
エンジニアならではのコツとして、HandBrakeのコマンドラインを使って一括処理用のスクリプトを組んでおくと便利です。最初はお試しでひと手間加えてみてくださいね。
古いMacでもスムーズに書き出すコツは?
古いMacだと書き出し中にファンが大きく回ってしまいがちですが、そんなときに頼りになるのがプロキシメディアの活用です。
元の動画より軽い解像度で一度データを作り直すことで、編集プレビューも書き出し工程もグッと軽くなります。メモリやCPUへの負荷を抑えられるので、古いMacでも落ち着いてサクサク作業したいときにピッタリです。
まとめ
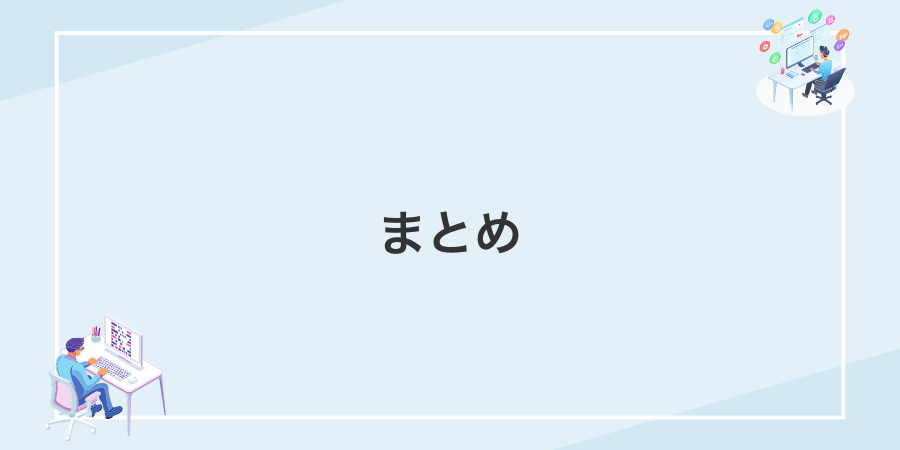
iMovieで動画を書き出すときは、まずタイムラインを選んで右上の共有アイコンから「ファイル」を選び、解像度や品質を決めて書き出し先を指定するだけで完了します。
これだけで自分のパソコンやクラウドにスムーズに保存できるので、SNSや動画サイトへのアップロードも手軽です。さっそく手順を試して、あなたのクリエイティブな作品をたくさんの人に届けてください。